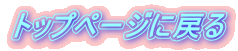岐阜県揖斐川町
*参考資料 『日本城郭体系』 『岐阜の山城ベスト50を歩く』
*参考サイト 城郭放浪記
揖斐城(揖斐川町三輪)
 *鳥瞰図の作成に際しては『岐阜の山城ベスト50を歩く』と現地案内板を参考にした。
*鳥瞰図の作成に際しては『岐阜の山城ベスト50を歩く』と現地案内板を参考にした。
揖斐川町三輪の一心寺の北側にそびえている比高180mほどの山稜部分が揖斐城の跡である。
揖斐城はよく整備されており、遊歩道が付けられている。その登り口は山麓の揖斐小学校にあるということだが、手っ取り早しのは、山稜中腹にある一心寺の先の金毘羅神社の祭られている先端部(その名も城台山公園)まで車で行くというルートである。
金毘羅神社の所には車を停められるスペースもあるので、ここに車を停めて歩きだす。一心寺の本堂の左側に回り込んで行くと、そこからちゃんとした登山道が付けられている。
後はこの登山道を登って行けばよい。一心寺からの比高は120mほどであるから、しばらく登って行けばすぐに白山神社との分岐点の所に出る。
白山神社経由でも、登山道をそのまま登って行っても、どちらにせよ城内に到達するので、好きなルートを選んでいけばよい。
やがて真っすぐが「揖斐城」、右が「井戸跡」という案内の所に差し掛かる。ここが城の入口である。井戸に興味がある人はそのまま右手に降りていってもいいのだが、井戸に降りるルートは、この先の4郭の手前辺りにも付けられているので、城内をざっと回った後で、井戸経由でこの地点まで戻ってくるのが効率的なルートである。
ここから2段ほどの段郭を抜けていくと、2郭下の腰曲輪の城塁が見えてくる。腰曲輪に入って見ると方形の石列のようなものが目に入ってくる。何でも明治年間に火災に遭うまで、ここに寺院の施設が存在していたのだという。石列はお堂が建てられていた名残なのであろう。
ここから見る2郭の城塁は非常に急峻で高くそびえて見える。2郭に登るルートは左右の両側に付けられている。
2郭は広く削平されており、中央部に土壇があった。ここに「史跡揖斐城跡」と刻まれた石碑が立てられており、「本丸」という案内板もある。しかし、私はより奥にあって地勢が高く防御性も高い1郭の方が主郭だと思ったので、ここはあくまでも2郭ということにしておく。
2郭の東側は枡形虎口になっており、その先には大きく竪堀が掘られているため、土橋が削り残されている。土橋の先が尾根状の郭となり、その先の一段高い所に1郭がある。ただし、現地の表示ではここは「二ノ丸」となっている。
注目すべき遺構は1郭の北側の下にある。北側下には帯曲輪があり、さらにその下に大きな横堀が造成されているのである。斜面が急峻なので、ここを降りていくのは大変だが、上から見ても、しっかりとした横堀であることが分かる。
この堀は内部に攻め込んできた敵を城塁の上から攻撃するための迎撃空間だったものと思われる。鋭い城塁を目の前にしては、敵は逃げ場を失ってしまうであろう。
横堀の東端には竪堀が入れられており、そこから北側には小さな帯曲輪が何段も造成されている。ここまで降りてくるのが大変だったのだが、横堀の東端部まで来てみたら、そこから3郭まで続く山道が付けられているのを見つけた。
1郭の南側に尾根は延びており、そこに数段に造成された郭が展開している。3の辺りである。それを進んで行くと、正面に高台が見えてくる。これが4郭である。
4郭の虎口も枡形状になっている。また、北側には帯曲輪、東側には横堀を配している。南側に延びていく尾根にも堀切を入れて分断を図っている。北東側や南側の尾根から接近する敵は、この4の所で足止めを食らうということになる。
4の下から北東側にも尾根が延びている。この先には長い土橋を中央に残した大きな堀切がある。その先に小郭があるが、これがこちら側の城域の末端を示すものであろう。
4郭から3郭方向に戻って行くと、ここからも井戸へのルートがあった。帰りは井戸経由で最初の入口まで戻って行くこととする。井戸に向かう途中の道の側面部の一部には石積みが見られた。
降って行くと岩を掘り抜いたような井戸が存在していた。今でも水を湛えている。実際にこれでどれだけの水量を確保できたのかよく分からないが、籠城の際に城内に井戸があるかどうかは、城兵の死命を制する重要な要素である。峻険な山城であるというだけではなく、このように水場を確保しているということこそが、堅固な山城の重要な要素と言ってもいい。
揖斐城は、全体に鋭く加工されており、防御性の高さを感じさせる山城である。枡形、横堀といった意匠もそれぞれよくできている。またしっかりとした井戸が存在している、といったように、実戦的な山城であったというべき城である。一見の価値はある山城だと言ってよい。城マニアは一度は訪れてみてもよいだろう。
 |
 |
| 南側から遠望する揖斐城。ここからの比高は180mほどある。 |
中腹先端部にある金毘羅神社。ここに車を停められる。ここからの比高は110mほど。 |
 |
 |
| 一心寺の背後から登って行くと、城の入口の所に出た。右側に降ると井戸に行ける。 |
2郭下の郭。 |
 |
 |
| 2郭から下の腰曲輪を見たところ。 |
2郭側面部の虎口。 |
 |
 |
| 城址碑。現地案内板ではここを本丸としているが、2郭だと思う。 |
2郭北側の枡形虎口。 |
 |
 |
| 土橋を通って1郭へ。 |
その先の郭の側面部にある石積み。 |
 |
 |
| 西側下の腰曲輪。 |
1郭だが、現地表示は二ノ丸となっている。 |
 |
 |
| 1郭下の横堀を見下ろしたところ。 |
横堀北端部の堀切。 |
 |
 |
| 横堀を内部から見たところ。1郭の城塁が高く鋭い! |
ここから北東側下に小規模な帯曲輪が何段も造成されている。 |
 |
 |
| 3の部分。 |
その先に大手門の表示がある。 |
 |
 |
| 4郭城塁。 |
4郭内部。現地表示は出丸跡。 |
 |
 |
| 4郭から北側下の横堀を見下ろしたところ。 |
4郭下の横堀。 |
 |
 |
| 現地表示ではここを北の丸としている。。 |
4郭の北東側先の堀切。中央部が土橋となって削り残されている。 |
 |
 |
| その先の郭は出丸となっている。 |
出丸から土橋越しに4郭方向を見る。 |
 |
 |
| 大手門跡から井戸に降りていく。通路の側面部には石積みが見られる。 |
井戸。現在も水が溜まっている。 |
 |
|
| 揖斐城内の入口付近にある白山神社。 |
|
揖斐城を築いたのは土岐頼清の子、頼雄であったと言われている。康永2年(1343)のことである。その後、揖斐土岐氏は揖斐氏を名乗って当地の豪族となった。
その後、約200年にわたり揖斐城は揖斐氏の居城として活用されていた。
天文16年(1547)、齋藤道三は、土岐頼芸を国外に追放した。その際、土岐氏に加担した揖斐氏は、齋藤道三に攻撃されることとなり、齋藤勢の前に揖斐城は落城してしまう。
揖斐氏の没落後、その家臣であった堀池氏が揖斐城を継承して居城とした。堀池氏は斎藤氏と内通していたのであろう。
永禄10年(1567)、織田信長はついに美濃攻略に成功した。その際、堀池氏は抵抗したようで、信長家臣となった稲葉良通によって揖斐城は攻略されて落城した。
その後、、良通の子、貞通が揖斐城の城主となった。
稲葉氏による揖斐城支配は近世に入るまで続いたが、慶長5年の関ケ原役の後は、西尾嘉教が入部し揖斐藩3万石の領主となった。
元和9年(1623)、西尾嘉教は死去したが嗣子がなかったため西尾氏は廃絶となり、揖斐領は幕府領となった。
寛永8年(1631)、旗本岡田善同が5300石で揖斐に入部した。岡田氏は揖斐城を廃して、山麓に揖斐陣屋を築いて居館とした。 |
小島(おじま)城(木戸尾城・揖斐川町春日六合)
 *鳥瞰図の作成に際しては『岐阜の山城ベスト50を歩く』と現地案内板を参考にした。
*鳥瞰図の作成に際しては『岐阜の山城ベスト50を歩く』と現地案内板を参考にした。
揖斐川町春日六合の郵便局の上方にある山稜が小島城の跡であり、googlemapにも掲載されている。城内には遊歩道が整備され駐車場も完備している。途中の道路の何カ所かに案内表示があるので、近くまで来れば場所は分かるであろう。
案内板には「小島城 天空の遊歩道」などと書かれている。しかし天空の遊歩道と言うのは実際は城のある場所ではなく、西側の天空の茶畑の辺りを指しているのかもしれない。そちらの方がよほど眺望が良さそうなのである。しかもこの高所にけっこうな数の民家のある集落が営まれている。まさに隠れ里のような場所である。これはこれで訪れてみるべき価値のある場所かもしれない。
小島城も遊歩道が整備されており、駐車場もある。この場所である。だから車は安心して停めて置くことができる。
駐車場に行ってみたところ先客がいた。何と千葉ナンバーの車が停まっていた。「千葉県からきている人がいるのかな?」と思いながら歩き始めた。
城の中腹のBの辺りには宗教施設のようなものがあり、そのためそこまで舗装された車道が付けられている。とはいっても関係者以外の車の乗り入れは禁止されているようで、一般の人は駐車場に車を停めて舗装された道を歩いて行くことになる。
谷戸部を越えて進んで行くと、やがて大きな竪堀が見えてきた。どうもこの竪堀が城域を区画しているもののようで、竪堀沿いにいくつも帯曲輪が形成されているらしい。
竪堀の先にAの施設のある郭があった。Aの下方にも小郭があり、その下は小規模な堀切によって尾根部分を切り離し、側面部には竪堀も入れている。
そこから進んで行ったところがBの施設のある郭である。この部分が城内で最も広い郭となっており、重要な施設が置かれていた場所であったと思われる。この下の郭にも何かの施設が建てられている。
この辺りから下方を見ると、何段も段郭が連続しているのが見えてくる。この部分の下方にも郭が多く展開しており、その先端部分には、枡形を有した虎口が存在しているようである。
Bの郭からは山道を登って行く。道は時に切通しになりながら上方に向かっていく。その際に側面部にはいくつもの腰曲輪状の郭が造成されているのが目に入ってくる。1つ1つはそれほど大きなものではないが、何しろ郭の数が非常に多い。
これは家臣団の集住を意識したものなのであろうか。城主が土岐氏であったことを考えると、それなりに多数の人員を配置するだけの空間を必要とした、と言うように考えるのが自然であるかと思う。
何段もの郭を登って行った後、登城ルートは山の斜面を横切って西方の竪堀のところまで進んで行くようになっている。
そこで人に会った。よく見たら、千葉城郭研究会のAさんではないか! Aさんと会ったのは10年ぶりくらい。この邂逅にはびっくりした。同じ千葉の城マニアと関東の城址で会うことならありそうな気がするが、遥かに離れた岐阜県の山城で会うとは、これは驚きである。Aさんからは「上の竪堀の近くに、しっかりとした石積みがあった」ということを教えていただいた。ここで聞かなかったら見落としたかもしれないので、この情報はとてもありがたかった。
横移動した登城道は西方の竪堀の所から切通しの通路を通って1郭に向けて登って行く。その側面部に比較的大きな3段の腰曲輪が存在していた。この辺りが城の中でも最も中枢に当たる部分である。城主や重臣に関する施設はこの辺りに置かれていた可能性が高いと言える。
やがて1郭の側面部を抜けると1郭背後の堀切の所に出た。土橋は長く側面の竪堀もかなり大きく掘られているが、背後から土橋を渡ってしまえば簡単に1郭に取り付けてしまう。尾根背後からの攻撃はほとんど想定していなかったようである。
背後部分からは1郭に簡単に登れる。1郭は円形状だが長軸20mほどもなく、主郭としては小さな印象である。土塁も何もない。ここは物見台といった施設を置いた場所であったかもしれない。
1郭から切通しの道を再び降って行く途中の下にある帯曲輪に降りてみた。Aさんに教えていただいた通り、この方向には多数の石積みがあったようだ。その多くは崩落してしまったようで石がたくさん転がっていたが、現在でもしっかりと残っている部分もあった。小島城は石垣も多用した山城であったのである。
小島城の構造はやや古臭い感じがするのだが、郭の数が多く石積みも残している。土岐氏の居城と言うだけあって、勢力者によって築かれた大規模な山城というべき城である。
 |
 |
| 3月下旬ということもあって、小島城周辺の山には山桜が咲き乱れていた(この山は小島城ではない)。 |
小島城の駐車場。何台も停められる。千葉ナンバーの車が停まっていたが、ここで偶然知り合いと会うとは思わなかった。 |
 |
 |
| 宗教施設のところまで舗装された道路を歩いて行く。 |
途中で竪堀が見えてきた。西側の大竪堀で、城域を画するものである。 |
 |
 |
| 休憩所の先の下にも段郭が造成されている。 |
ここから登って行くと多数の段郭が見えてくる。 |
 |
 |
| 竪堀状の通路。 |
これも段郭。 |
 |
 |
| 段郭の間の切通しの通路。 |
西側の竪堀のところまで平行移動する通路。ここで千葉城郭研究会の知人と偶然出会った。こんな山城で知り合いに会うとは・・・偶然というのはあるものなのだなあ。 |
 |
 |
| 2郭と城塁。 |
1郭に続く通路。 |
 |
 |
| 1郭背後の堀切。 |
1郭背後の堀切中央部の土橋。 |
 |
 |
| 1郭内部。 |
2郭西側下の石積み。 |
 |
 |
| その下にはもっとしっかりとした石積みが残っていた。 |
通路の側面部下の石積み。 |
 |
 |
| Aの施設の下のテラス状郭脇の竪堀。 |
そのさらに脇にある竪堀。 |
鎌倉時代の正和年間に、小島城には西尾氏が在城していたと言われるが詳細は不明である。
その後は、土岐頼貞の子頼清が分家して小島領を拝領し、その子の順康が小島城を築いて城主となった。このような山間部にどうして居城を置いたのかはよく分からない。平地だと敵に攻め込まれてしまう心配があったのだろうか。
建武4年(1337)の軍忠状に「木戸之尾」で合戦があったことが記されているという。「木戸之尾」とは小島城がある尾根のことを指す地名であり、ここで合戦があったことが伺える。詳しい状況についてはよく分からないが、土岐氏は幕府方の武将として活躍しているので、南朝方との一戦がこの地域であったということなのだろう。
康永元年(1342)、頼康は土岐本家を相続した。後光厳院が美濃に逃れて来た時には小島頓宮を造営して天皇を迎え入れた。
頼康の跡を継いだ土岐康行は明徳元年(1390)に小島城において乱を起こした。その際には京極高秀らの幕府軍に攻められ小島城は落城した。
その後、幕府軍側にいた土岐頼忠が美濃守護となり、新たに本郷城を築いて居城としたため、小島城はその必要性を失っていったようで、その後史料には登場してこない。
ところが、発掘の結果を見ると、遺物は16世紀のものまで出土している。ということは戦国期にも小島城は使用されていたのである。16世紀ということになると、土岐氏、斎藤氏、織田氏までがその使用範囲となってくるのだが、具体的に史料に出ることはないので、誰がどのように活用していたのかはよく分からない。 |
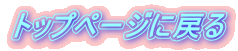
 *鳥瞰図の作成に際しては『岐阜の山城ベスト50を歩く』と現地案内板を参考にした。
*鳥瞰図の作成に際しては『岐阜の山城ベスト50を歩く』と現地案内板を参考にした。




























 *鳥瞰図の作成に際しては『岐阜の山城ベスト50を歩く』と現地案内板を参考にした。
*鳥瞰図の作成に際しては『岐阜の山城ベスト50を歩く』と現地案内板を参考にした。