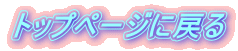
中世城郭における天主とは何か・・・『信長公記』を参考に 2020.5.15
天守といえば、城を象徴する建造物であり、一般の人は「城」=「天守」であると思っている人が多い。城マニアではない一般の人と話をしていると、「〇〇城には城はないんでしょ?」と言われる場合、天守が(現存・復元・模擬を問わず)存在していない城を示しているという経験をしている人は多いであろう。また、天守のような建造物のない城を「城ではなく城跡」というように思っている人も多い。
かくも、城といえば天守、というイメージが一般にしみ込んでしまっているのだが、もともと「天守」とはどのような建造物を示していたのであろうか。近世城郭よりも以前の中世段階における天守のイメージを探してみると、既存の天守のイメージとは違ったものが見えてくる。『信長公記』に描かれた天守のイメージから、その時代の天守がどのように認識されたいたのかについて検討してみたいと思う。
ただし、『信長公記』の諸本を校合したわけではない。底本として用いたのは新人物往来社版の『信長公記』である。
実は『信長公記』には「天主」という用語は比較的頻出する語句であり、全体で15カ所確認することができる(「天守」という語句は存在しない。この文章では天主と天守とを区別して書いている)。それらについて1つ1つ見ていきたい。
最初は、p60-6巻首「家康公岡崎の御城へ御引取りの事」にある部分。
「清洲北矢蔵、天主、次の間にて・・・・(勘十郎を)御生害なされ候」 これは信長が弟の勘十郎信勝を殺害するシーンである。一見して意味が通らないような表現となっている。ここでの天守とはどのようなものかということについては後述するとして、清洲城に北矢蔵というものが存在していたということは分かる。この場所で勘十郎は殺害されたのである。
p71-7巻首「武衛様と吉良殿と御参会の事」を見ると、
「武衛様国主と崇め申され、清洲の城渡し進ぜられ、信長は北屋蔵へ御隠居候ひしなり。」
とあり、武衛様(斯波義銀)を奉じて清洲城を奪取した後の信長は、清洲城の本丸御殿を斯波義銀に譲り、自らは北矢蔵というところに居住していたということが分かる。つまり、この北矢蔵は信長の居館であり、そのことを「天主」と呼んでいるようなのである。信長が居住するような矢蔵であるから、通常の矢蔵というよりは、清洲城の中でも象徴的な建造物であったと想定してもよいのではないか。
p79-1巻首「堂洞の取手攻めらる々のこと」この箇所では、以下の2文の中に天主という語句が登場してくる。
「二の丸を焼き崩し候へば、天主構へ取り入り候を」
「川尻与兵衛天守構へ乗り入り、丹羽五郎左衛門つ々いて乗り入るところ」
美濃の攻略の前哨戦の堂洞城攻めの記述である。「二の丸を焼き崩し候へば、天主構へ取り入り候を」というのは堂洞城の主要部に織田軍が突入する場面である。また続く「川尻与兵衛天守構へ乗り入り」は、川尻与兵衛が一番乗りをしたことを示している。天主構という名称で出てくるのであるが、天守構とはどういったものだろう。他の箇所で「外構に乗り込み」といった表現も見られることからすると「構」=「曲輪」のようだ。
つまり「天主構」=「本丸」であり、天主とは本丸にあった城の中心をなす建造物を示していると考えられる。堂洞城はごく普通の中世山城であるから、近世城郭のような天守などあるはずもない。規模は不明だが、中心となる建造物が存在していて、それを天主と呼称しているだけなのだと思われる。
ちなみにこの章では太田又助という武士が活躍して信長に賞賛されているのだが、この太田又助こそ『信長公記』の著者である太田牛一である。つまり、この部分は『信長公記』の作者の実体験を描いてある項目であるということになる。
p115-10巻3「志賀御陣の事」
「御天主へ御上り候て、霜月21日、織田彦七御腹めされ、是非なき題目なり。」
次は巻3の「志賀御陣の事」。ここでは長島の一揆に対抗するため織田信長の弟孫七が「こきゑ」の城を築いたことが書かれている。「こきゑ城」とは愛知県愛西市にあった古木江城のことである。しかし、志賀の陣で織田軍の主力が動けないでいる隙を突いて長島一揆勢が古木江城を包囲すると、援軍も得られないまま城は落城寸前となる。そこで孫七は「一揆の手にかかり候ては無念」として「御天主へ御上り候て」切腹して果てることになる。
城主が最後に切腹する場所であるのだから、ここではやはり城の中心となる建物のことを天主と称していると考えられる。御天主と「御」を付けているのは、信長の弟である孫七への敬意を示したのであろうか。古木江城は、平城で現在ではまったく遺構も見られなくなっている城である。やはり近世城郭のような天守が存在するはずはなかろう。
ただ、平城であるがゆえに物見のための高い建物が必要であったとも考えられる。城主が居住するような中心的な建造物に2階があり、そのような建造物のことを『信長公記』は天主と呼称しているのかもしれない。このような建造物が古木江城の中心的建造物であったということを想定してみよう。
p152-8巻6「阿閉謀叛の事」
「天主の下まで攻め込み候のところ、叶ひがたくおぼしめし」
次は巻6「阿閉謀叛の事」この部分は前後のつながりが分かりにくくなっているのだが、その後に河内若江城のことに触れていることから、若江城で反乱がおきた際の場面であると思われる。「天主の下まで攻め込み候のところ、叶ひがたくおぼしめし」といったように反乱軍が天主の下まで攻め込んできたことが知られる。この記述では天主のイメージをまったく知ることができないが「天主の下まで」とあるのだから一定の高さを持った建物だったように思われる。
若江城もまったくの平城でり、時代柄、単層の建造物が中心であったろうが、その中にもいくらか高い建物があり、その下まで攻め込んだことを「天主の下まで」というように表現したのであろう。物見櫓のようなものであったろうか。
次がいよいよ安土城である。安土城に天主があったことに疑問を感じる人は皆無であろう。安土城の天主の記述は5カ所あり、安土山御天主(巻9)、御天主へ御移徒(巻12)、御天主見物仕り候て(巻12)、安土御殿主(巻14)、御天主(巻16)となっている。詳細は以下の通り。
p191-5巻9「安土の御普請首尾仕るの事」
「安土山御天主の次第」
安土城の完成後、天主の内容を具体的に示している場面である。
p249-14巻12「二条殿・・・・病死の事」
「五月十一日、吉日に付き、信長、御天主へ御移徒(わたまし)。」
信長が安土に帰って、天主に渡ってきたという記述。
p257-14巻12「赤井悪右衛門退参の事」
「御天主見物仕り候て、」
天正7年7月26日、石田主計と前田薩摩の両名が安土に招かれ、堀久太郎のところで接待されている場面。その後、御天主を見物して、「このような結構なものは見たことがない。生涯の思い出である」などと言っている。
p328-6巻14同前
「七月十五日、安土御殿主、并びに、総見寺に桃灯余多つらせられ」(ここのみ表記が御殿主となっているが意味は同じであろう。)
天正9年7月15日、安土での祭りの様子。安土御天主や総見寺に桃灯(提灯)を多数つらせて飾り立てていた。その様子は湖面にまで映って、非常に素晴らしいものであったという。戦国時代にもライトアップがあったのである。安土城の全山ライトアップ!これは私もぜひ見てみたかった。
p388-12 巻15「江州安土城御留守居衆の有様の事」
「御天主にこれある金銀・太刀・刀を取り、火を懸け、罷り退き候へと、仰せられ候ところ」 本能寺の変の後の展開。この後、安土城からは出火し、天主を含め大同伽藍ことごとく焼亡してしまうことになる。ただし、誰が安土城に火を懸けたのかについては触れていない。留守居をしていた蒲生氏が引き揚げた後、空き城となった城内に夜盗やら様々な連中が入り込み、分捕りを行っているうちに出火したと考えるのが順当である。
これらの表記を一見して気が付くのは安土城天主に関してのみは、すべてが「御天主」と「御」を付けているということである。信長に対する敬意があったのはもちろんのことながら、これは安土城の天主が他の城の天主とは別物であることを示しているのではないだろうか。他の箇所の天主は織田孫七が切腹した古木江城を除いては、すべて「天主」と表記されており、「御」は付けられていない。これまで見てきた中世城郭の「天主」と安土城の「御天主」が別物であるということにも異論はないだろう。
p211-7巻10「信貴城攻め落とさる々の事」
「松永、天主に火を懸け、焼死候。」
続いて巻10、松永弾正が謀反して信貴山城を攻める場面である。織田軍に包囲された信貴城の松永弾正はもはや抵抗はできないとあきらめて「松永、天主に火を懸け、焼死候」となるのである。松永弾正の最期といえば、天主の火薬に火を懸け爆死したとよく言われているが、『信長公記』ではあくまでも焼死となっている。爆死説については、何を根拠としているのかは分からない。
このように信貴山城には松永弾正の建てた天主があり、これが日本の城の天主の始めであるという説が昔からある。出典は肥前平戸の藩主松浦静山の書いた『甲子夜話』にある話である。『甲子夜話』は東洋文庫で全20巻と非常に大部であり、かつてこの記事を探したのだが発見できなかった。そこには「松永弾正の築いた信貴山城には天主があり、これが日本の天主の濫觴である」と言ったことが書かれているのだという。
『甲子夜話』が書かれたのは文化年間の甲子の年からであるから、江戸時代も後期になってからのことである。松浦静山が「信貴山城が天守の濫觴」と書いたことの根拠としたものが何であったのかが気になるところである。おそらく何らかの伝承に基づいたものであったろうが、すでに戦国時代からは遠く、根拠薄弱であるともいえる。だから、実際に多層構造の天守が存在していたのかどうかは確信が持てない。ただ、他の部分での記述と同様、松永弾正が最後に立てこもるほどの城の中心となる建造物があり、それを天主と表現しているということまでは間違いない。
『信長公記』から想定できるのは、中世城郭での中心的な建物というだけのものであるから、本当に信貴山城に一般に言われるような4層の高層建造物が存在していたとまでは言い難い。実際に信貴山城を訪れた際にも、天守台のようなものを確認することはできなかった。
p226-9巻11「播磨神吉城攻めの事」
「先ず一番に城楼(せいろう)高々と二つ組み上げ大鉄砲を以て討ち入り・・・・城楼をあげ、大鉄砲以て、塀・矢蔵打ちくずし、屋蔵へ火をつけ焼き落とし・・・手前々に城楼・築山をつき、日夜責めらる。」
三木城攻撃の前哨戦として神吉城を攻めた時の記述である。秀吉軍は、「城楼(せいろう)」を築いて砲撃し、神吉城の「塀・矢蔵打ち崩し」たとある。城楼は高層建造物であるが、これに対しては天主という表現は用いられず、城楼から攻撃した対象についても単に「矢蔵」としか表記していない。
p227-7同前
「神吉民部少輔討ちとり、天主に火を懸け、込み入り込み出だし、戦ふ事、火花を散らし、其間に天主は焼け落ち、過半、焼死候なり。」
しかし落城のシーンになると天主が登場してくる。「中の丸へ攻め込み」「天主に火を懸け」「天主は焼け落ち」落城してしまうという流れになっている。ここでは天主の文字が続けて2か所に見られる。記述内容からして中の丸は本丸を示しており天主に火を懸けたことが落城のエポックイベントとなっている。やはり天主が本丸にあり城の中心的建造物であったことを示しているといえる。
神吉城も現在、明確な遺構は残しておらず、近世城郭のような天守が存在したはずもない城である。ただ形状は不明ながらも城の中心となる建造物は存在しており、それを『信長公記』は天主と呼んでいるということである。
p239-7巻11「安部二右衛門御忠節の事」
「二右衛門城の天守へ、両人取り上げ、居城候。」
続いて巻11「安部二右衛門忠節の事」の記述。荒木村重の謀反のくだりの辺りで、尼崎城の支城で大矢田城というのが出てくる。詳細はよく分からないのだが、大矢田城の「天主へ、両人取り上げ(人質を入れて)」というように出てくる。
尼崎城の支城の大矢田城がどんな城であったのかまったく未見である。しかし、それほど有名な城ではないことに間違いないだろう。そのようなマイナーな城ですら、その中心的な建造物のことを天主と呼んでいるのである。
p265-8巻12「伊丹城謀反の事」
「城楼かねほりを入れ、命御助けなされ候へと」
ここでは天主は出てこない。織田軍が伊丹城の攻撃に際して城楼を建てたり、トンネルを掘ったりして攻城戦を行っているのだが、城楼のことは天主とは表現していない。これは城の中心的な建造物ではなかったからであろう。
p327-6「因幡国鳥取城取り詰めの事」
「二重・三重の矢蔵を上させ・・・・・矢蔵を丈夫に構へさせ」
最後に巻14の鳥取城包囲戦の場面。鳥取城を包囲するために秀吉が長陣を構築したことはよく知られているが、その部分の表現として「透間なく、二重・三重の矢蔵を上させ」とある。二重・三重の矢蔵といえば高層建築であり天主のイメージに近いものである。この時代に三重の櫓が存在しているのであれば天主と呼んでも差し支えはないだろう。しかし、これらを天主とは呼んでいない。
天主とはあくまでも城の中心をなす建造物のことであり、三重の櫓であっても城の中心物でなければ天守とは呼称されないということである。城の中心となる建造物の一般的な呼称として『信長公記』の作者は天主を使用している。この作者の見方が普遍的なものだとまでは言えないが、近世城郭的な天守でなくても、城の中心となる建物は「天主」と呼ばれていたのだという可能性は検討するに値するであろう。つまり、ごく普通の中世城郭においても「天主」と呼ばれるものが存在していたということができる。これは一般的な天守のイメージとはだいぶ異なっているものである。
城マニアではない一般の方が城=天守と思い込んでいるのと同様に、城マニアであっても、天守=近世城郭的な高層建造物と思い込んでしまっているのではないだろうか。ここまで見てきたとおり、実際にはそれほど立派なものではなくても城の中心的な建造物であれば「天主」と呼ばれていたというのが実態であった。
このことから城マニア自身も、天主という用語が本来どのようなものであったかを再認識する必要があるといえるのではないか。我々自身も天守という語句の既存のイメージを脱却することで、本来見えていなかったものが見えてくるのかもしれないのである。
ちなみに安土城天守を「天守」ではなく「天主」と表記するのは「天下人である信長がその意気を示すためのものであった」とか「天主(デウス)を城内に祭ったから」といった論があるようだ。しかし、ここで見てきたとおり、天主と表記されているのは安土城に限らず、普通の中世城郭にあるものもみな天主と表記しているのだから、信長やデウスには関係がなく天主は存在していたわけであり、その論には根拠がないということが理解できる。
これは『信長公記』の作者の書きぐせなのかもしれないが、とにかく天主と呼ばれるようなものは、戦国時代にはあちこちの城に存在していた。あるいは天主と天守の違いは「中世城郭の中心建造物」と「近世城郭の中心建造物」ということにあるのだろうか。だとすれば「天守」は誰が造語したものなのだろう。今回はそこまで調べていない。
ふりかえって冒頭の、織田信勝が殺害された場面を再確認してみる。「清洲北矢蔵、天主、次の間にて」という文章が最初、意味の取りにくいもののように思われてしまったことからこの論は始まっている。しかし、天主が中世城郭の中心的建造物を指すものと理解したら、
「清洲北矢蔵、天主、次の間にて」のくだりは、「信長の住む清洲城の北矢蔵すなわち天守の次の間において」信勝は殺害された、というように普通に意味の通る文になるのである。『信長公記』の作者が言いたいことは、そういうことなのだろう。
ところで、『信長公記』には岐阜城の形状について表現した部分がないので、岐阜城の天主に関する記述は出てきていない。しかし岐阜城の信長居館に4重の高層建造物が存在していたことはルイス・フロイスの記録から確認されている。
この天主に関してはその形状には諸説あるが、少なくとも高層建造物であったことは間違いなく、天下布武を目指す信長の意気軒昂ぶりを人々が伺い知ることのできる象徴的建造物であったと言える。
岐阜城にも清洲城にも天主が存在していたとするなら、その中間点に当たる小牧山城においてはどうだったであろうか。小牧山城に関しても『信長公記』にはその形状を表現するような描写は残されていない。
しかし近年の発掘の成果から、本丸から4間四方の櫓台が検出されており、そこに城を象徴するような建造物が存在したであろうことは間違いないとされている。4間四方だとすると、ぜいぜい2重の構造物であろうか。これも天主といっても差し支えないものである。
先に信貴山城が天守の始まりであるという説を紹介したが、それを信長が参考にして安土城の天主を築いたという説もある。しかし信長は、清洲城、小牧山城、岐阜城と、その居城のほとんどに天主を置いているのだから、別に松永弾正を参考にしたわけではなく、安土城も信長の独創だったとみてよいだろう。
最初の天主といえば、伊丹城の天守がそうであるという説も昔からある。それは『細川両家記』に「家々へ火をかけ、てんしゅにて腹切りぬ。」という記述があることによる。これは永正17年のことなので、この時点で天守が存在していたということになれば、確かに相当に古い時代の話であり、画期的な構造物である。しかし、ここまで見てきたとおり、中世城郭においては、その中心となる建造物を天主と呼んでいるにすぎない。
つまり、そのような建造物はあちこちに存在していたはずであり、伊丹城の場合はたまたまそれが『細川両家記』に「てんしゅ」と記録されているだけのことである。だから最初の天主はどれか、という問いかけは実は全く意味のないものである。
しかし、近世城郭的な意味での天守の嚆矢が安土城であることは間違いないところである。そういう意味では本邦最初の天守は安土城とするのが正しいと言える。その点でも信長はエポックメイキングな存在であったというべきである。
『細川両家記』の「てんしゅ」の記述は「しゅでん」の誤記ではないかという説もある。しかし、主殿にしたところで、ここで述べてきた天主と意味合いはそれほど遠くない。『信長公記』に登場する天主の多くは「主殿」と読み替えても意味が通じるものの方が多い。
『信長公記』に「主殿」がどのように出てくるかも見ていたのだが「御殿」「御屋敷」は多数出てきたが「主殿」と書かれているものは1つもなかった。主殿は少なくとも『信長公記』の用語には存在しない。主殿と天主との関係についても、いろいろ調べてみると興味深い結果が出てくる可能性もある。
さて、ここでいったんまとめておく。『信長公記』から天主がどのようなものとして描かれているのかを考察してきた。結果として言えるのは、この書に登場してくる天主のほとんどが、近世城郭のイメージにある天守とはまったく異なったものであったようだということである。
最後に『信長公記』以外の同時代史料に出てくるものも紹介しておこう。
『北条五代記』 小田原の役の直前の場面の小田原城の様子を描く場面で、「惣がまへに堀を掘り、土井石垣の上にせいろう矢倉すきもなし、所々の角々には殿主を立をき、白壁は天にかがやき」とある。ここでの殿主は、井楼櫓とは別物と区別され、白壁造りであった、というようになっている。
近世城郭の櫓に近いイメージであったと思われるが、城の中心的な建造物でなくても複数建てられていた高層の櫓を殿主と呼んでいる。『北条五代記』の著者の三浦浄心は父子三代にわたって北条家に仕えた人物で、慶長年間に大部の記録『見聞集』を残していて『北条五代記』はそこから北条氏に関する部分を抜粋したものである。関東で一般的であったとまではいかないが、浄心は高層の櫓=天守と考えている。このように天守の定義は人や地域によっても異なっていたのである。
城マニアも知らず知らずのうちに天守=近世城郭の天守というイメージに支配されてしまっているが、実際に戦国時代に天主と呼ばれていたものは、もっとささやかな建造物であったケースの方が多かったのである。城マニアにとって「天守」という語句は常識的な城郭用語となっているが、戦国時代当時には我々が想像するものとは異なった用法で用いられていたのである。