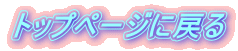
「上田原合戦」「戸石崩れ」に見る『甲陽軍鑑』のリアリティ
07.10.30
『甲陽軍鑑』は甲州流軍学の教本として近世に広く流布した作品であり、武田氏の歴史を知るために広く読まれてきた作品でもある。かつては多くの歴史小説や歴史解説書がこの書を参考にしていた。しかし、その内容については以前から疑問視されている。内容に誤りが多く、奥書にあるような「高坂弾正」の作ではないのではないかというのである。実際、『甲陽軍鑑』には明らかな誤りが非常に多く、高坂弾正がそのような間違いをするはずもないので、実際の作者は高坂ではなく、甲州流軍学の祖である小幡景憲の創作物にすぎない、などというようにもいわれてきていた。
『甲陽軍鑑』が、高坂筆を装った偽書であるという説は、実は古くからあり、すでに近世初期にはそのような話が伝えられていた。次に紹介するのは『武功雑記』の一部である。
『武功雑記』ではまず戦国期、上方で兵法の大家であった上泉伊勢守について触れている。上泉伊勢は弟子の虎伯をつれて、大和に行った。そこで柳生但馬守親父と対決するが、弟子の虎伯、上泉いずれも柳生に勝利した。そこで、柳生は、上泉を師として仰ぎ、3年間大和に留め置いて、新陰流を開眼した。
その後、上泉は関東に下るということで、三河の国に寄った。その三河牛久保の牧野氏の領内に「きょう流」を使う山本勘介という兵法の達人がいた。牧野が山本勘介と上泉を対決させたところ、上泉が勝った、といった話である。
ここでの山本勘介は地元の人間に好かれていなかったらしく、「勘介をにくしと思ふものは、勘介がうたれたりと沙汰のみなり。勘介これを不気味に思ひ、いとまもらひ甲州へ行く」とある。「いい気味だ」といった具合に言いふらされて、いたたまれなくなったのである。
その後甲州に赴いた勘介は、「兵法はつかふ口おもなれば」(剣の腕前も口も達者だったというのであろう)、武田の武将山縣が抱え置くことになった。川中島合戦の時に、山縣は勘介を斥候に遣わし、それを報告する様子を信玄が見て「あれは何者ぞ」と問うたので、山縣は「あれは山本勘介とて三河もの也。口おもなるものとて、山縣扶持しおきたり」と答えた。『武功雑記』はさらに続けて「此外沙汰あるものにてはなし」と述べている。つまり山本勘介は武田の一武将山縣の斥候であったに過ぎず、川中島で偶然見かけるまでは信玄も知らない程度の人物であったのであり、それ以上の者ではなかったというのである。そして、次に『甲陽軍鑑』に触れている。
「勘介の子、関山派の僧にて学文ちとありしが、甲州信州の間にて信玄の事など覚書して置きたる反故などを取り集め、吾親の勘介事を結構につくりかきたるなり。是を高坂弾正が作といつはりて書たるなり。是僧後に井伊掃部頭殿家中に甲州者の居たるにたより、弥(いよいよ)甲州のことなどさし集めて甲陽軍鑑と名をつけしなり」
『武功雑記』は肥前平戸藩主松浦鎮信の著で、元禄9年(1696)頃の成立であるという。松浦家は大阪浪人や、加藤・福島の浪人ら200余名を召抱え、戦場生き残りの武功者の聞き書きなどを積極的に収集した。それを取りまとめたのが『武功雑記』であり、『国史大事典』を見てもこの書は「比較的信憑性は高い」と紹介されている。ただ、当時すでにもてはやされていた甲州流軍学や『甲陽軍鑑』に対しては批判的な立場であったようで、『甲陽軍鑑』や山本勘介に対して意図的におとしめるかのような書き方をしているように見える。しかし、近世にすでにこのような説が流布していたという点は注目すべきことである。
山本勘介は『甲陽軍鑑』において武田信玄の軍師のような立場で活躍する人物であるが、ちゃんとした史料にはほとんど出て来ない人物である。あれほどの活躍をしておきながら史料で確認できないことから、かつては『甲陽軍鑑』の作者によって捏造された人物であるとも言われてきた。しかし昭和44年、「市河文書」が発見されたことから、実在性が高まってきた。それは次のような文書である。
「注進状披見、仍て景虎、野沢の湯に至り、陣を進め、其の地へ取り懸かるべき模様、また武略に入り候といえども、同意無く、あまつさえ備え堅固ゆえ、長尾功無くして飯山へ引退き候ゆえ、誠に心地よく候。いずれも今度、其の方のはかり頼もしき迄に候。なかんずく野沢在陣のみぎり、中野筋後詰めの義、飛脚に頂き候き。すなわち倉賀野へ越し、上原与三左衛門尉、また当年の事も塩田在城の足軽を始めとして、原与左衛門尉五百余人、真田へ指し遣はし候処、既に退散の上是非に及ばす候。全く無首尾有るべからず候。向後は兼て其の旨を存じ、塩田の在城衆へ申し付け候間、湯本より注進次第に当地へ申し届けるに及ばず出陣すべきの趣、今日飯富兵部少輔の所へ下知を成し候の条、御心易く有るべく候。猶山本菅助口上有るべく候。恐々謹言。(原漢文) 六月廿三日
晴信(花押)
市河藤若殿」
日付はないが、内容からして川中島合戦の頃のものであることは明らかである。市河氏は現在の栄村(野沢温泉辺り)を領していた一族であった。この辺りは信州と越後との国境近くであり、川中島よりもさらに北部に当たる。川中島で越後の長尾景虎と対峙していた当時、この地域の領主を味方につけておくことは武田にとって最重要事であった。
この文書によると、長尾景虎が野沢地域に攻め込んだが、市河氏がよく守りきったことについて褒めている。今後何かあったときは、甲州に連絡せずに塩田城の兵が駆けつけるように手配しておくと言って、市河氏を安心させようとしている。そして最後に「猶山本菅助口上有るべく候」と締めくくる。つまり市河氏への使者として山本菅助を送り、彼に詳しいことを述べさせるというのである。
この文書では「勘助」の「かん」の字が異なっているが、当時は当て字がよく用いられているので、字が違っていたとしてもたいした問題ではない。それよりも「山本かんすけ」という人物が実在していたことがこの文書によって確認されるということの方が重要である。同姓同名の人物がそう何人もいたとも思われないので、これが『甲陽軍鑑』の山本勘介のモデルであったと見てよいであろう。
いつ敵に寝返るかもしれない豪族の慰撫は重要な任務であり、その役目を担わされていた山本菅介はある程度信玄に重用されていた人物だった、と想像できる。
先の『武功雑記』においては、「信玄は、川中島で初めて山縣の使い走りであった山本勘介を見知った」となっていたが、これは勘介を少しおとしめすぎであり、実際には山本勘介は信玄から直接指示を受ける程度の立場であったようだ。その意味でも『武功雑記』は山本勘介と『甲陽軍鑑』を意図的に褒貶しようとしているようである。したがって『武功雑記』の記述にも一種のフィルターがかけられており、すべてをそのまま信用することはできない。
さて、この文章のテーマは、『甲陽軍鑑』は「史実を正しく述べる」という観点から見て、リアリティがある書だと言えるのかどうか、ということである。
実のところ、私は以前から『甲陽軍鑑』(新人物往来社版)を読んでいて、「これだけ大部の書であり、多くの情報を掲載しているのだから、当時、高坂など当事者の書き残した素材が存在していて、それに基づいて書かれたものであり、史料として使用できる部分も多いのではないか」と想像していた。しかし、より信用できそうな史料と比較しながらその細部を読んでいくにつれ、最近では「どうもそうではないようだ」という気持ちに傾いてきている。
しかし、近年、『甲陽軍鑑』は再び、史料として脚光を浴びつつもある。何しろ『甲陽軍鑑』にしか現れてこない事象も多いわけだから、吟味した上でそれを有効活用しよう、という発想は非常に前向きである。そのきっかけとなったのは国語学者の酒井憲二氏による研究であり、酒井氏は『甲陽軍鑑』の諸書を検討した結果、戦国期に甲斐でしか用いられていなかった方言なども多用されており、『甲陽軍鑑』の基本資料は戦国期に甲斐で書かれたものに間違いないだろうと結論をまとめている。それゆえ、『甲陽軍鑑』は奥書にある通り、高坂弾正の覚書が基となったものであり、春日惣次郎がそれを引き継ぎ、小幡景憲はそれを補綴しただけで、内容の改ざんには関わっていない、というように話は広がっていく。しかし、果たしてそうだろうか。
『甲陽軍鑑』には次のような奥書がある。
(品第六)
天正三年乙亥六月吉日 高坂弾正「忠」
長坂長閑老
跡部大炊助殿
「参」
(品第十)
天正三年乙亥六月吉日 高坂弾正「忠」書之
いずれも作者を示すものであり、高坂弾正が書いたもだと明記するものである。天正3年6月は長篠の合戦の一ヵ月後であり、長篠合戦での敗北を受けて、武田勝頼の重臣「長坂・跡部」の二人に宛てて書いたという体裁になっている。『甲陽軍鑑』全体を通して、「高坂」は「長坂・跡部」に対して批判的であり、この両者に宛てているのは、両者を諌めるために書いた、という意図の表れでもある。
ちなみに長篠での軍議の様子は「品第52」で次のように描かれている。
「然ば彼長篠にて、武田の家老馬場美濃守、内藤修理、山縣三郎兵衛、小山田兵衛尉、原勇人佐各老共に申し候は、御一戦なさるる事御無用なりと種々申上候へども、御屋形勝頼公と長坂長閑、跡部大炊助は、一戦なされてよしとある儀なり」
武田家の功臣たちが口を揃えて決戦を諌めたというのに、長坂・跡部らは無謀にもそれを主張したという。これによって長篠で決戦を挑んだ武田勢は大敗北を喫した。当時、越後の押さえに留守居していた高坂弾正は武田軍の敗北の知らせを聞いて、勝頼を途中まで迎えに出ていったと述べている。
長坂らへの批判はその他にも出てきており、「品第53」の高天神城攻めにおいても
「長坂長閑、跡部大炊助、戌の年東美濃、遠州高天神にて合戦も、彼両所身の上悪く有べきと存候。末の考えもなく弾正異見を長坂長閑讒言いたし、妨にてかくの如くに候」
とある。
このように『甲陽軍鑑』は長篠での負け戦を踏まえて、その1ヶ月後には、長坂・跡部に対して意見するような形で成立したということを奥書は示しているのだが、このような大部の書がそんなに短期間で書き上げられるものであろうか。
(品第四十下)
天正三年乙亥六月吉日 高坂弾正書之
(右石水寺物語一巻に付て九十六ヶ条上下合百九十二ヶ条なれ共、少々きれてすたる。残ルをまとめて書立事、小身の愚人尾幡勘兵衛尉景憲而記之)
これも高坂弾正が書いたという記述は同様だが、その後に注釈が付けられている。『石水寺物語』というのが1巻について96か条、上下巻合わせると192か条あったのが(つまり全2巻)、あちこち切れて破れていた。それらをまとめて補綴したのが尾幡勘兵衛尉景憲すなわち小幡景憲であったと記している。この記述を信じるならば、小幡は「破れていた本を補修して後世に残した人物」という位置づけになる。
また『甲陽軍鑑』のネタ本の名称が『石水寺物語』2巻192条であった、ということも知ることができる。このことからすると、『石水寺物語』こそが高坂弾正の残した書置きということになるだろうか。
(品第五十三)
高坂弾正存生の時・・・・・
天正五年丁丑年十二月吉日 高坂弾正書也
「高坂弾正存生の時」以下は長いので省略したが、この奥書は一読して違和感を感じる。これを書いているのは高坂弾正であるというのに「高坂弾正存生の時」という表現はおかしいのではないだろうか。この表現は死んだ人の生前を偲ぶときの書き方であり、高坂自らが書いたとはどうも思えない。
(品第五十九)
此軍鑑書続たる我等は春日惣次郎と申候。川中島皆景勝へ召出され候へ共、我等は甲州くづれの時分、越中へ罷越候故、景勝へ御か々への衆にはづれ候而牢籠いたし、佐渡の沢田といふ在郷にをひて是を書置、三十九歳極月より積を煩、長四十の年三月中旬に死する也、仍て如件
天正十三年乙酉年三月三日 高坂弾正内
春日惣次郎
高坂弾正は天正6年に死去しているので、それ以後の部分はそれを書き継いだ人物の手になるということになる。そのことを示しているのがこの奥書である。「品第54」には
「其年(天正6年)三月より高坂弾正膈を煩い、存命不定也。去に付、是より以後は、弾正父方の甥、春日惣次郎是をかきつくるなり」
とある。これによって春日惣次郎は高坂弾正の父方の甥であったということが分かる。
天正10年(1582)、武田氏が滅亡すると(甲州崩れ)、武田の遺臣のうち川中島近くにいたものは上杉景勝に召しだされたが、自分は越中に逃げたため景勝に召しだされることもなく浪人となり、佐渡の沢田にいて、これ(『甲陽軍鑑』)を書き置いた。そして39歳の12月から積(癪)を患って、40歳の3月中旬に死亡した、とある。
この書き方もとてもおかしい。「自分は40歳の3月に死亡した」などという文言を本人が書くなどということがありうるであろうか。死亡する直前に死の運命を悟って書いたという解釈もあるのかもしれないが、文章としては非常に不自然である。本人以外の者が書いていると見るのが自然であろう。
奥書により作者とされている高坂弾正とは、だいたい次のような経歴の人物であった。彼はもともとは春日源助といい、武田晴信に仕えて後、いくつかの武功を挙げて春日弾正と名乗りを変え、川中島の海津城代に任じられるようになった。その頃、武田に背いて誅罰された高坂(正しくは香坂であるという)氏の名跡を継ぎ、高坂弾正と名乗るようになった。海津地方を治めるのに、高坂の名跡を継ぐのが都合がよいと考えたのである。永禄4年(1561)頃のことであるという。しかし、彼はすぐに名乗りをもとに復し、春日弾正と名乗るようになる。天正6年5月7日に川中島で病没した。
といった具合。ここでもっとも注目されるべきなのは、『甲陽軍鑑』において高坂弾正という作者名で出てくるこの人物が、実は天正年間にはすでに春日弾正とその名乗りを旧姓に戻していたという事実である。つまり、『甲陽軍艦』の奥書にある天正3年から5年の頃には、彼は春日弾正であったはずであり、高坂弾正という名を用いて書を記していること自体が不自然だということである。
さらに、『甲陽軍鑑』で、武田勝頼に全面攻撃をそそのかして武田軍を敗亡させたとして批判されている長坂長閑は、史実では甲斐の留守居役であり、長篠の合戦には参加していないという。となると、同時代に生きた春日弾正の記録として、『甲陽軍鑑』の内容には矛盾を感じざるをえないであろう。
こうした部分からだけでも、『甲陽軍鑑』を高坂弾正が書いたというのには大きな疑問がある。さらに、『甲陽軍鑑』には史実と矛盾した記述が多いと書いたが、それには単なる記憶違いではすまないものも多く含まれている。そこで、今回は天下無敵と呼ばれた武田晴信が2度にわたって敗戦を経験した「上田原の戦い」「戸石崩れ」の二つの事件を通して、高坂弾正作者説の矛盾点について考えていきたいと思う。
永禄期以前の武田氏については史料がとても少ないが、比較的信用できる史料として用いられているものに『妙法寺記』『高白斎記』がある。『妙法寺記』は甲斐都留郡にあった寺院の古記録。『高白斎記』は、武田晴信に仕えた家臣駒井政武の残した記録であり、いずれも同時代史料である。このうち『高白斎記』には、後世になって『甲陽軍鑑』に基づいたと思われる竄入部分があちこちにあって注意を要するが、それらを取り除いた部分は比較的信用できると思われる。
これらの史料に基づいて、上田原合戦、戸石崩れの発生年時等をまとめると以下のようになる。
(1)上田原の合戦・・・・・・天文17年(1548)2月14日
『妙法寺記』『高白斎記』ともに日時は共通。『王代記』も同じ年月である。
これら3つの史料がいずれも天文17年2月14日という現在でいえばバレンタインデーの日の戦いであったことを示しており(ただし『王代記』には日は記されていない)、この日付で間違いないものと思われる。上田原の戦いは真冬に行われた合戦であった。
なお、『妙法寺記』はこの戦いを「塩田原での戦い」としている。塩田原も上田原もだいたい同じような場所を指していると思われるので、この表記の違いについてはそれほど問題としなくともよさそうだが、合戦の名称としてはどちらをとるのがふさわしいだろうか。
これらの記録内容は具体的には次のようになっている。
『妙法寺記』
「此年(天文17年)の2月14日に信州村上殿近所、塩田原と申す所にて甲州の晴信様と村上殿合戦成され候。去程にたがひに見合せ川を小楯に取り候ひて、軍をいれつ乱れつ食され候。去程に甲州人数打ち劣けて、板垣駿河守殿、甘利備前守殿、才間河内守殿、初鹿野伝右衛門殿、此の旁(かたがた)打ち死に成され候ひて、御方は力を落し食され候。去共、御大将は本陣にしはを踏み食され候。小山田出羽守殿、比類無き働き成され候。御上意様にかせててをおひ食され、去間一国の歎き限りなし。去れ共軍止まず」
『高白斎記』
「(天文17年2月)14日庚申 板駿・甘備其外討死。」
さらに
『王代記』(山梨市の窪八幡宮の記録)では
「(天文17年)信州村上一戦、板垣駿河・甘利備前討死、二月」
『妙法寺記』には明確に甲州勢の負けであると書いている。『高白斎記』の方はごく簡単にしか書いていないが、板垣駿河と甘利備前といった2大将の討ち死にを明記しているのだから、甲州勢にとって手痛い合戦であったことは間違いない。この書物は事実を淡々と記述していくところに特徴があり、「勝った」だの「負けた」だのといった書き方はしていない。ただ、「○○落城」「○○討ち死に」といった記述方法で、いかにも記録として書かれたらしい文面となっている。
なお、板垣駿河守を板駿、甘利備前守を甘備といったように、名前を最初に一文字ずつとって省略するのは、この当時の文書でごく普通に見られることであり、特別なことではない。
『高白斎記』について補足しておくと、この書の天文17年の部分に、『甲陽軍鑑』とほぼ同じ内容の記述が見られる。しかし、これは上記の「竄入」にあたる部分で、無視してよいと思われる。
続いて戸石崩れの合戦についてみてみる。
(2)戸石崩れ
『妙法寺記』では天文19年の9月1日、『高白斎記』では天文19年の3日から9日にかけての出来事となっているが、実際の攻城戦は数日に渡って行われていたと考えられるので、数日の誤差はそれほど問題ではない。要するに天文19年の9月初旬に戸石城の近辺で合戦があったということである。両書の記述を見ると以下の通り。
『妙法寺記』
「此年(天文19年)9月1日に信州戸石の雲戒(要害)を御のけ候とて、横田備中守を始とし、随分衆千人計打死成され候。されとも御大将は能く引き食され候」
『高白斎記』
「(天文19年9月)3日、砥石の城ぎはえ御陣寄せらる。9日己亥 酉刻より砥石の城を攻らる。敵味方の陣所へ霧ふりかかる。未の刻、晴る。」
いずれも武田の負け戦と明記してはいないが、『妙法寺記』では侍大将である横田備中守を始めとして千人ほども討ち死にしたとある。この当時の戦で千人も討ち死にするなど、こっぴどい負けっぷりといっていい。例によって『高白斎記』では合戦のあったことは記しているが、勝ち負けについては触れていない。ここでの『高白斎記』の描写は比較的詳しいが、それでも合戦内容の詳細は読んだだけでは理解しにくい。ともあれ合戦の日時は『妙法寺記』とほぼ一致している。
これらのことから、この2つの合戦について実際の事件の流れとしては
(1)天文17年の2月14日に村上との間に上田原合戦が起こり、武田勢が敗北。
(2)その後、武田氏は態勢を立て直すが、2年後の天文19年9月に戸石城近辺での合戦で武田勢は再び村上勢に敗れる。
といった具合であったということになる。
さて、次に『甲陽軍鑑』での合戦の時日を見てみよう。まとめると次の通りである。
戸石崩れ・・・・・・・・ 天文15年(日にちは「切れて見えなかった」ようで空欄になっている。後段から見ると3月であったようだ)
上田原の合戦・・・・・天文16年8月24日
なんと、合戦の起こった順序が反対になっている。しかも真冬の戦いであった上田原合戦が真夏も真夏、8月24日に起こったこととなっている。これをどうみるべきであろうか。
確かに、昔のことを思い出して記録を書いていく場合に、記憶違いによる書き間違いというのは起こりがちである。われわれにしても、「三億円事件」「浅間山荘事件」「よど号のっとり事件」などがそれぞれ、昭和何年のことか思いだしてみよ、と言われても、すぐ明確に年号を答えることは難しい。
しかし、自分にとって非常に印象的だった出来事については、少なくともその順序を間違えることはないと思うのである。たとえば「結婚して次の年に長男が生まれて、さらに翌年に長女が生まれた」といったことを「長女の方が先に生まれて、翌年に長男が生まれた」などと、間違えることはないし、「結婚した翌年に子供が生まれた」といったことを「子供ができたので、仕方なく、できちゃった婚をした」といったように勘違いすることもないであろう。物事には流れというものがあるのである。上田原合戦で負け、その後小笠原攻めを行って態勢を立て直して再度戸石城に攻めこんだが再び敗れたといった、これだけ大きな事件の順序を当事者に近い立場にいた人間が取り違えるなどということが起こりうるであろうか。
上田原の合戦にしても同様である。真冬の戦いであった合戦を、うっかり勘違いで真夏の戦いであったと書いてしまうなどというのは、勘違いにしても程が過ぎる。少なくとも合戦に参加した当事者かそれに近い立場にいた人物がそのようなミスを犯すとはとうてい思えないのである。
この2つの合戦は武田晴信にとって手痛い負け戦であった。ところが『甲陽軍鑑』を読んでいくと、結局、このいずれの戦も最終的には武田の勝ち戦としている。武田びいきという点を差し引いたとしても、かなり史実とは遠い記録になってしまっている。
私はこうした矛盾を、単なる「作者の記憶違い」というように解釈することはできない。記憶違いにしては不自然でありすぎる。これには勘違いではなくある種の意図があったのではないか。つまり、この間違いは、「うっかりそうなってしまった」といったものではなく、「意図的に書き変えられた結果によるもの」だと思うのである。そうでなければ真冬の戦いが真夏の戦いになるなどといったことは起こりえない。
ではなぜ、『甲陽軍鑑』において、戸石崩れが上田原合戦の先に来ており、真冬の上田原合戦が真夏の合戦に変更されているのか。それにももちろん理由があるわけなのだが、それについては後で述べることとして、まずは『甲陽軍鑑』におけるこれら二つの合戦の内容について、詳細に見ていきたいと思う。
*『甲陽軍鑑』における戸石崩れ
天文15年 月 日に戸石城攻めが行われる。(品第二十五では、日付はこのように空欄になっている。切れていて読めなかったようだ。ただし戦いの後の部分で「3月11日御馬入」)とあるので、3月に起こったこととしている)
まず武田の諸将の陣立てが描かれているが、村上義清が6000の兵を率いてくると、すぐさま楽岩寺の兵200騎が先駆けして甘利衆に攻撃をしかけ、合戦が始まった。横田備中の子息彦十郎は16歳の初陣だったが、見事に敵を討ち取った。
その後甘利衆に、村上方の5勢力が襲い掛かってくる。そこに戸石城内の村上勢も加勢したために、甘利備前・横田備中の両大将は討ち死にしてしまった。武田勢が苦境に立ってきたところで、山本勘介の登場となる。
その時山本勘介は徒歩足軽25人を預かり旗本に属していたが、武田勢の苦境を見て自分の部下を他の足軽大将に預け、勘介は晴信の御前に参上した。そこで申し上げた内容は
「村上はただいま、御旗本に攻め懸かり一戦を遂げようとしています。甘利備前・横田備中は討ち死にし、甘利の家中には手負い怪我人が多く出ていますが、晴信公の威光ゆえにいまだに崩れたってはいません。しかしいくら強いと言っても、それほど長くは持ちこたえられないでしょう。甘利衆が崩れる前に、何とぞご分別ください。」
晴信は答える
「信州先鋒勢と味方とが入り乱れており、それがしの下知もままならない。とどのつまり、残った小山田勢、諸角勢とそれがしの三備えで一合戦して、信州勢を討ち果たすより他に方法はないだろう。」
そこでさらに山本勘介は言った。
「敵の軍勢の向きを南に向けることができれば、この合戦は勝ち申す」
「味方さえ思うように動かせぬというのに、味方の思惑で敵を南に向けるなどとは今まで聞いたこともない」
「後ろの諸角の馬乗り50騎を勘介の思うように使わせていただければ、武略ができ申す」
そこで晴信は勘介を連れて諸角のところに行き、勘介を引き合わせた。諸角は「そのような武略は聞いたこともない」と言ったが、晴信の命に従い、勘介に兵を預けた。ここから勘介の武略が始まるのだが、ここから先は原文によって紹介する。
「勘介、諸角衆をつれて道5町ほど出て、備えをたつるを、敵見て案のごとく人数をまとめ、切所をこしてかからんとする。敵かかりはせずして南へ向く。敵南へむけば、味方の御旗色、悉くなをりて、備えしぐらむ。味方しぐらむと一度に敵軍さやけくなり候。是を勘介みて、御旗本へ参り、晴信候御意を得奉りて、御旗本・足軽衆半分と、小山田備中手勢70騎と合わせて、一戦を持てかかる。又、備中一備にてかかるを見て、敵、敗北なり。」
このような感じで、結局、武田勢は勝ったという話になってしまっている。この勘介の武略、諸角の兵を預かるまでは場面がよく理解できるのだが、肝心の武略のシーンでは、具体的に勘介が何をどうやったのかさっぱり理解できない。読む人の読解力不足ではなく、どう読んでもなんだかよく分からない書き方をしているのである。
しかし、勘介のこの武略によって武田が勝利したので、世間の人は「山本勘介武略の故と、上下共に山本勘介を摩利支天の様に申す。」とある。さらに、
「敵を討ち取る数、193は雑兵合わせてかくの如し。味方は信州先方衆へかけて721人、雑兵共に討ち死にするなり。されども、敵は少しも足をとめずして敗軍仕る。晴信公軍の場をふまへ、勝時を執り行い給へば、是も勝合戦なり。下々のさたには、屋形様御機嫌あしかるべし、と諸人存の外、少もさなくして晴信公御機嫌一段よく御座候て、3月11日に御馬入、帰陣ましまして」
といったように続いていく。
この勝利は山本勘介の武略のおかげだと人々はみなうわさしたというのである。ただし、討ち死にした人数は敵が193、武田が721、人数的には武田の方が負けているようだが、晴信公はその場に踏みとどまって勝鬨を行ったのだから、これは武田の勝ちであると主張する。晴信公の御機嫌が悪かったといううわさもあるが、それは間違いで、実際には晴信公は機嫌がよかったのだ、そういった内容である。
この合戦、実際には武田が負けていると思われるわけであるが、『甲陽軍鑑』はそれを武田の勝ち戦というように話を作り変えていると見られる。とはいっても、実際の討ち死に数は武田がはるかに多く、そのため晴信の機嫌が悪かったと言う人々のうわさについても触れている。あるいはその辺りは、『甲陽軍鑑』が拠った本来の記録に基づいているのかもしれない。しかし、これだけ話が作り変えられていると、本来の記録がどのようなものであったかを想像することすら難しい。そして、そのような勝ち戦の原因を作ったのが山本勘介であるというのが、『甲陽軍鑑』の記述の特徴の1つなのである。
これは一種の創作である。
このような話の作り変えは、どういう意図によって行われたものなのであろうか。いくら武田ひいきとはいえ、負け戦を勝ち戦にまで転換させなければならない理由があったのであろうか。もしあったとしたら、それはどういう立場の人間であったと見るべきだろうか。
想像するに、このことには、『甲陽軍鑑』が甲州流軍学のテキストとして用いられていたということが大きく関わっているのではないかと思う。江戸時代にあって甲州流軍学がもてはやされたのは、武田晴信の合戦を学ぶことにより戦いに勝つための極意を身に付けることにあるのであって、そのためには晴信には勝ってもらわなければならない。そう、武略によって彼が勝つ場面を欲していたのは、甲州流軍学を講じるべき立場にあった人間である。
先の山本勘介の武略のシーンについても同様である。いくら『甲陽軍鑑』をよく読んでも、山本勘介が具体的にどのような武略を用いたのかさっぱり理解できない。『甲陽軍鑑』が普通の記録文学であったならば、山本勘介の武略の内容についてもきちんと描こうとするであろうし、そうしていたならば、このような抽象的な記述で終わってしまうということはない。
しかし、『甲陽軍鑑』を軍学のテキストとしてみた場合、いかがであろうか。テキストだけ読んでも分からない部分を講義で補う、というシステムを取り、しかもそれを秘伝である、というようにして伝授したとすれば、軍学塾の経営的な観点から見ても、こうした書き方ははなはだ理想的であるとさえいえる。塾で講義を受けた人だけが、山本勘介の秘術を知ることができるのである。このように考えてみると、軍学塾で購読するテキストとして『甲陽軍鑑』は非常に都合のよい構成になっているとさえ言える。
このように見てくれば、本来の合戦の記録を作り変え、『甲陽軍鑑』に見られるような内容に仕立て上げたのが誰であったかということは、おのずから明らかになってくるようだ。この書を軍学のテキストとして利用しようとした人物、すなわち小幡景憲こそがその当事者であろう。負け戦を無理に勝ち戦に改変したり、山本勘介を登場させて武略をさせておきながら、その内容を抽象的にしか描写しない、そういったことをする必要性があったのは高坂弾正でもなければ、春日惣次郎でもない。それを行って利を得る人物は小幡景憲であったろう。
*『甲陽軍鑑』における上田原合戦
次に上田原合戦についてみてみる。(ちなみにこの戦いを上田原合戦としているのは、先にあげた資料のうちでは『甲陽軍鑑』だけであり、『妙法寺記』では「塩田原」での戦いとしている。『甲陽軍鑑』の記述では年号も時季も史実と異なっているということからすると、本来この戦いは「塩田原の合戦」とする方が適当であるのかもしれない。ただし塩田原も上田原も、ほとんど同じような場所であるので、それほどこだわらなくともよいのかもしれないが。)
『甲陽軍鑑』にある記述内容を以下に記す。
天文16年8月2日に武田晴信は甲府を立ち、同月6日に佐久郡志賀城を取り詰めて、同11日には同城を攻め落とした。
それを聞いた村上義清は、「このままでは村上旗下の人々も心が離れてしまう」と思い、「ここで武田晴信を討ち果たさなければならない」という決意の下、総勢7000人で出陣した。旗下の人々の申し様は「去年、真田弾正の知略のために村上家中の弓矢の誉れある人が大方殺されてしまった」ということでこの戦には反対するものであった。しかし村上義清はそれに耳を貸さない。さらに村上衆が「今回の武田の人数は多勢でありご遠慮なさるべきである」というと、義清は「30にもならない晴信は相手をするほどの者でもないが、是非、旗本をめがけて晴信と自らが勝負するか、あるいは先年武略された遺恨に、真田の頭を刀の切っ先に掛けるか、2つに1つである」と思い切っていた。
そうして無理に村上が出ると聞いて、村上旗下の侍は三ヶ二(三分の二)は出なかった。村上殿は1万にもおよぶ人数を有していたが、7000余りにて出陣することになった。(7000余りの兵が出陣したというのだから1万の三分の二が出陣したということになるが、ここは作者の単純な記述ミスであろうか。)
そうして信州上田原に出て、8月24日の辰の刻(午前8時)に甲州方から合戦を始めることとなる。武田の先方は板垣駿河守であった。真田も先陣を希望したが、晴信は「村上は先年、真田の武略で被官をあまた殺されて口惜しく感じている。だから合戦の勝負にかかわり無く真田弾正の備えを見つければ、そこに無理に一戦を仕掛けてくる。真田を討たせてはどうかと思う」と村上の心を読んで見せたので、「晴信公は古今まれなる弓矢取りの大将である」と人々は感じ入った。
先陣の板垣は3500の人数で一戦を始めて村上勢を追い崩した。板垣の手勢だけで敵を150ほども討ち取ったのである。板垣は弓矢巧者の者であったが、それですっかり油断してしまい、逃げた敵がまたすぐに押し寄せてくるかもしれないような危険な場所で首実検を始めてしまった。そこへ案の定、村上勢が押し寄せてきた。板垣勢はあわてて武器を取ろうとしたが、備えを立てる間もなく、武辺に慣れた信濃武者にすきも無く取り囲まれてしまう。
敵は板垣の姿を見知っていると見えて、床机に腰を据えていた板垣に向かって一目散に攻め寄せてくる。板垣は馬を引き寄せ乗ろうとしたが、乗らぬ間に左右から槍を付けられ、転んだところで首を取られてしまった。
こうして板垣勢は敗軍したが、武田の旗本7備えのうち栗原左衛門が真っ先に進んで村上勢を押し返した。さらに飯富兵部、小山田備中、石田の小山田、御舎弟典厩らが勇んで、村上勢を切り崩した。村上義清は700人ほどになり、味方の敗軍を脇に見ながら晴信の旗本の方へ面もふらず攻め寄せた。それによって晴信公の旗本は3町ほど後退した。
だが脇備え・後備えの馬場民部、内藤修理らが横筋かいに入り立って、武田の旗本と合戦していた村上勢をことごとく追い散らした。その間に諸角、真田、浅利の三手は、村上義清が逃げようとする所を襲い、敵を討った。また、原加賀守は、旗本の5,6町後にいて、300ほどの人数で見物のように控えて備えを立てていた。
そして次に山本勘介が登場してくる。
「此、三河牢人山本勘介、晴信公に申し上げる、軍法かくの如し」
これだけである。これでは勘介がどのような内容のことを晴信に進言したのか、さっぱり分からない。しかし、戸石崩れの記述で見たように、勘介の武略に関する部分の表現はこれでよかったのであろう。勘介が進言したその具体的な中身は、塾での講義の中で説明すればよいのである。このようにこの部分での山本勘介の言動も、『甲陽軍鑑』の講義をするのに適合した形になっていると見ることができる。
さて、村上勢は敗色が濃くなってきており、旗本が四方へ突き散らされていた。にもかかわらず、村上義清は、晴信公と互いに馬の上で渡り合い、両者、刀の切っ先から火炎を出して斬り戦った。両者の馬は逸物であったが、太刀の光におびえてしまい、村上が近寄ろうにも遠立ちをする有様で、そのうち周囲に武田勢がしだいに増えてきた時に、村上義清は落馬してしまった。そこで村上衆の14,5騎が、雑兵4,50を引きまとめ、落馬した義清を包んで丸くなって退却し、深山に入り込んで、それから越後に逃れ入った。後で聞くと、「あの時晴信公と太刀打ちしたのは村上義清自身であった」という。村上は出陣の際の公言の通りにしたのであり、「つよき大将なり」と近国他国で評判となった。
この合戦の勝利によって武田は小県奥4郡を手に入れた。晴信公27歳の時のことである。中でも、この合戦が5度に分かれていたというのは、板垣が初戦に勝ったのが一度目、村上方が二の合戦に勝ったのが二度目、飯富兵部が三の合戦に勝ったのが三度目、村上が武田旗本に攻め掛かり、武田勢を3町ほど押しやったのが四度目、馬場民部が采配をふるって村上義清旗本を蹴散らしたのが五度目である。
結局武田の勝利であり、その日申の刻(午後4時)には首帳を付けて、討ち取った数2919をもって申の刻の終わり頃に勝鬨を執り行った。味方も雑兵合わせて700ほど討ち死にした中でも、名誉の大将板垣信形が討ち死にしてしまった。晴信公も薄手を2箇所負ってしまった。
ざっと要点をまとめるこのような感じである。この合戦も『甲陽軍鑑』では結局、武田方の勝ち戦ということになっている。実際には武田の負け戦であったのにもかかわらず、である。先の戸石崩れの段と同様、武田が負けては都合が悪いと思った人物による改変がここにもあったのである。
もう1つ、この合戦シーンを読んでいて特に印象に残るのは、武田晴信と村上義清が混戦のさなかで一騎打ちをしたという部分である。敵の大将と一騎打ち・・・・どこかで聞いたような話である。そう、永禄4年の川中島での、晴信と長尾政虎との一騎打ちのシーンとよく似ているのではないか。
川中島での両大将の一騎打ちはあまりにも有名である。それが有名であり、さまざまなドラマや小説などで描かれてきたこともあり、私自身、この一騎打ちは史実であった、いや、そうであったと信じたいといった気持ちでいた。このような大軍の合戦において、大将同士が太刀打ちするなどといったことが本当に起こりうるかどうかという疑問は昔からあったのであるが、「なにしろ長尾政虎のやることだから、一騎で敵の本陣に突っ込んでいくといったこともあったかもしれない」などとも思ってきた。
しかし、改めて上田原合戦のシーンを読んでみて、「やはり一騎打ちは創作だな」と思わざるをえなくなった。武田晴信が大苦戦した2つの大きな戦いで、それぞれ敵の大将と一騎打ちをするなどという偶然が果たして起こりうるであろうか。二度までこのようなことが起こるとはとても考えられないのである。
つまるところ、『甲陽軍鑑』の作者は、「大将同士の一騎打ちシーン」というものを描いてみたかっただけなのではないだろうか。混戦の中で一騎打ちをするところ、敵が去ってから「実はあれが敵の大将だった」と分かるところなど、2つの一騎打ちシーンには共通する点が多い。一騎打ちが史実であったというよりも、作者の好みの創作であったと考える方が自然であろう。
合戦の解説の内容、「戦いは5度あり、これこれは武田の勝ち」など、合戦を部分的に評価する解説の仕方も、第4次川中島合戦の後の「其合戦、卯の刻に始まりたるは大形越後輝虎の勝ち、巳の刻に始まりたるは甲州信玄公の御かち、越後衆を討ち取る其数、雑兵共に3117の首帳をもって、其の日申の刻にかち時を執り行い給ふ」とあるのによく似ている。この部分は、実際に同じような事態があったたため似たような記述になったというよりも、作者の好みで同じような表現にしたといった方が正しいのではないだろうか。
さて、このように史実では武田勢の敗軍であった上田原の合戦も、『甲陽軍鑑』では武田勢の勝ち戦ということにしてしまっている。勝ち負けだけならば、武田びいきの作者が勢いでつい書いてしまったということもありうるかもしれないが、すでに延べたように、実際にはこの合戦は真冬の2月14日に起こったものであった。それなのに『甲陽軍鑑』は真夏の8月24日の出来事としている。これは通常ありえない誤りであり、意図的な改変によるものである。
だとすると、『甲陽軍鑑』の作者は、どうして真冬の戦いを真夏の戦いに改変する必要があったのであろうか。そして、なぜ、この戦いが、史実と異なり、戸石崩れの後の出来事となっているのか。
それを解明する鍵は、「上田原合戦で敗れた村上義清がそのまま越後に逃げ込んで長尾景虎を頼った」という部分にある。上田原合戦を武田の勝ち戦に改変してしまったがゆえに、その後村上義清が越後に逃げ込むという流れに乗せてしまうしかなくなってしまったわけであるが、実際に村上義清が越後に落ちていったのは天文22年のことであった。『妙法寺記』には次のようにある。
「此年(天文22年)、信州村上殿八月塩田の要害を引のけ行方不明なり候。一日の内に要害16落申候」
天文19年の戸石崩れで再び村上勢に敗れてしまった武田勢ではあるが、その後次第に勢力を回復していき、3年後の天文22年にはついに村上義清を信州から追い出すことに成功した。それが天文22年の8月の出来事なのである。
村上義清が最後に拠点としていた塩田城は、上田原の南方に位置している城郭であった。すなわち天文22年の8月にも、上田原付近で争乱はあり、そこで武田は村上勢を追い落としているのである。おそらく『甲陽軍鑑』の作者は、上田原合戦を武田の勝ち戦に改変するために、実際に村上義清を追い落とした天文22年の戦いと上田原合戦を統合しようと試みたのであろう。その結果、この合戦が8月に起きたということに再設定された。
さらに、『妙法寺記』の天文15年の項には次のようにある。
「去程に城(志賀城)は水につまりて常州人数と合戦は8月6日。しが要害は8月11日。依田一門、高田一族、しが殿御内をはかろう平六佐衛門尉兄弟八人。去間、以上打ち死に300計。」
このように、天文15年の8月には佐久郡の志賀城が武田勢の攻撃を受けて落城している。さて、すでに述べているように、『甲陽軍鑑』の上田原合戦の前にも志賀城落城の記述はあった。『甲陽軍鑑』では8月6日に志賀城を取り囲み、11日に落城させたとあったので、『妙法寺記』の日時と微妙に共通しているのが分かる。しかし、『妙法寺記』に記述があるように、志賀城の落城は、『甲陽軍鑑』のいう天文16年ではなく、実際はその前年の天文15年であった。
『甲陽軍鑑』は、天文15年にあった志賀城落城の話を翌年のこととして上田原合戦にそのままつなげている。8月中旬に志賀城が落城すると、それを受けて出陣してきた村上勢と8月中旬に上田原で戦い、そして、そこで敗れた村上義清がそのまま越後へ逃亡する、といったように事件の流れを一時期に起こったことのように編集し直している。
その目的は、上田原の合戦を武田の勝利として作り直すことにあったのだろう。実際には武田晴信は、上田原合戦で敗れた上に2年後には戸石城でも村上勢に敗れるなど、数年にわたって、村上勢と丁々発止の争いを繰り広げていた。それを武田が有利であった歴史に改竄するために、天文15年の志賀城落城、天文17年の上田原合戦、天文22年の村上義清逃亡とを組み合わせて、村上との戦いは同じ時期の一連の事象であったように再構成しているのである。この流れであるのならば、武田が村上氏に苦戦していた時期はとても短いものになるし、天文22年の8月には村上氏は武田に敗れて越後に落ちていっているのは事実であるのだから、その話を混入させたことによって、上田原合戦で武田が村上に勝つという事象の捏造にもいくらかのリアリティを持たせることに多少は成功しているのかもしれない。
とにかくこうした編集作業によって、『甲陽軍鑑』においては、武田晴信は村上氏にさほど苦労することなく、信州の大半を手にしているかのような内容を作り上げることに成功している。
このように、上田原の合戦を真夏の戦いとしたのは、武田勝利の歴史を捏造するために事件の新しい流れを作ろうとする意図がその根本にあったからだと思われる。
それでは、なぜ、戸石崩れは上田原合戦の前に置かれているのか。
実際の歴史では戸石崩れは上田原合戦の後に起こっているわけだが、すでに述べたように、『甲陽軍鑑』では、上田原合戦で敗れた村上義清がそのまま越後に逃亡して行ったことになっている。したがって、上田原合戦の後に戸石崩れの合戦が来るのは不自然な配置になってしまう。そうしたわけで、戸石崩れは上田原合戦の前に置くしかなかったのである。そのため、この二つの合戦の順序が入れ替えられたのであろう。ここにも作者の編集の跡が見て取れる。
『甲陽軍鑑』がこのような歴史の流れを生み出してしまったために、その後の流れも史実とは随分違ってしまっている。村上義清の依頼を受けた長尾景虎が実際に信州に進攻してくるのは、『妙法寺記』では天文24年、『高白斎記』では天文22年のこととなっている。しかし、『甲陽軍鑑』では天文16年には長尾景虎が信州佐久郡まで攻め込んでくることになってしまう。史実よりもかなりの前倒しである。
『甲陽軍鑑』に表れた、武田との対峙の記録をまとめると以下のようになる。
1.天文16年(1547)10月6日景虎と晴信は信州海野平で合戦を行う。当時、景虎は18歳、晴信は27歳であった。
2.天文17年(1548)信州小県で景虎と晴信は12日間対峙する。
3.天文18年(1549)5月1日、景虎と晴信、信州海野平で5日対峙する。
4.天文19年(1550)9月28日から10月10日まで、信州海野平で謙信と信玄と対峙する。
5.天文22年(1553)8月、信玄は山本勘助に縄張りをさせて川中島に貝津城を築かせる。この頃、「景虎定まりて一年に一度づつ、川中島に働かるる」。
6.天文23年(1554)景虎、1万3千の軍を率いて川中島清野に出る。たいした戦いはなく、引き上げる。
7.天文24年(1555)3月5日、謙信川中島に出る。信玄も6日に川中島に到着するが、5日対峙した後に謙信は兵を退いた。
8.弘治2年(1556)3月28日、謙信、川中島に出てくる。4月中対陣していたが、5月になって謙信は兵を退いた。
9.弘治3年(1557)4月12日、謙信と信玄、川中島に出る。5月末まで対陣する。
10.永禄元年(1558)、謙信と信玄とは和解の話し合いを持つが不調に終わる。5月から閏6月半ばまで70日余り対陣する。
11.永禄2年(1559)2月、信玄は川中島に出る。謙信は3月に出てきて対陣する。4月2日、謙信は加賀・能登に出陣するために兵を退く。
12.永禄4年8月16日、謙信、川中島に出てくる。後はおなじみのいわゆる「川中島合戦」のよく知られた話が展開している。謙信は西条山に布陣し、信玄は山本勘助の進言にもとずいて、軍を2つにわけ、西条山を夜襲しようとする。(ただし、この戦法を「きつつきの戦法」とは呼んでいない。) しかし謙信はそれを察知して夜のうちに雨の宮の渡しを渡る。そして、決戦。謙信の陣の動かし方を不思議に思った家臣に対し「お前はそんなこともしらぬのか、あれは車懸かりといって、何廻り目かに、旗本と旗本が激突する戦法だ」といった。そして、信玄の本陣に萌黄の胴肩衣を着て、白手巾で頭を包み、月毛の馬に乗り、三尺の刀を手に持った武者が現れる。武者は信玄に3太刀切りつけ、信玄は8箇所に刀傷を負った。信玄の馬廻りたちが寄ってきたので、その武者は逃げていったのだが、後で聞いた話によると、その武者は謙信であったという。(この話は上述したように、大将同士の一騎打ちを描きたいという作者の好みによるものであると思われる。)
川中島の合戦(対峙)は合計5度あったなどといわれているが、『甲陽軍鑑』ではこの通り、なんと12度も対峙している。しかも4度目までは長尾影虎が海野平まで出陣してきている。これはさすがにありえない話である。上田原合戦の話を編集し、村上義清の没落を早めてしまったためにこのような描写を生じさせてしまったのである。もちろん、実際にはこれほど多くの対峙はあろうはずもない。他の史料と比べてみれば一目瞭然であるが、これらはほとんどでたらめな内容であるといってもいい。
さらにもう1つ、「上田原合戦」「戸石崩れ」の記述で、史実と異なっている要素がある。それは甘利備前の討ち死にについてである。史実では甘利は天文17年2月14日の上田原合戦で討ち死にしている。しかし『甲陽軍鑑』においては、彼は天文15年の戸石崩れで討ち死にしたということになっており、死亡した場所と年号が史実と異なっている。
これについても何らかの作為があるのであろうか?
しかし、残念ながら、この錯誤の理由についてはよく分からない。実際にこれらの合戦において甘利がどのような戦いを行い、そしてどのようにして戦死したのかがまったく描かれておらず、それゆえ錯誤の理由も何も、検討する材料がなさすぎるのである。
ただ、次のような想像はできる。『甲陽軍鑑』での戸石崩れの描写において、甘利の軍勢はかなりの活躍を見せている。戸石崩れにおける甘利勢のそうした活躍を描くために、甘利の戦死場所を戸石城にすることに何らかのメリットがあったのではないか。しかし、それが具体的にどういうことを意味するのかと言われると、検討する材料が少なすぎて何ともいえない。歯切れの悪いところである。
以上、上田原合戦、戸石崩れという2つの合戦から、『甲陽軍鑑』が史実をどのように描いているのかをざっと見てみた。史実と比べてみて感じるのは、この書に描かれている齟齬は、『甲陽軍鑑j』作者の記憶違いなどではなく、意図的な改変だということ。史実を力任せに改変することによって、都合のいいように歴史が塗り替えられてしまっているのが、『甲陽軍鑑』の中身である。そうしたわけで、この二つの合戦において『甲陽軍鑑』にリアリティを求めるのは無理であろう。この書の執筆に当たって、ある程度は当時の記録や覚書などが参考にされているのであろうが、実際にはかなり「作られて」しまっているようだ。
『甲陽軍鑑』の内容をこのように創作、あるいは編集し直したのは誰なのか?
それについてもすでに述べた通りである。武田勝利の歴史を軍学の講義として伝えようとしていた人物。軍学講義のテキストとして、より使いやすい形に内容を変えようとした人物であろう。それをする可能性が最も高いのは小幡景憲である。彼こそが、現在見られる『甲陽軍鑑』の内容を創作した人物の最有力者である、といえるのではないだろうか。
『甲陽軍鑑』の奥書によると、小幡景憲は、バラバラになりつつあった『石水寺物語』を補綴しなおした、ということになっている。また酒井氏の研究によれば、『甲陽軍鑑』の古い写本では「ここは切れてみえなくなっていた」といった書き込みがあちこちに見られるという。そうしたことから、小幡は、主観を入れることなく善良なる補綴を行っていただけなのではないか、という見方もある。
確かにこれだけ大部の書物を書くのに、何の材料もない状態ですべて自らの手で創作するというのは不可能であろう。小幡が軍学のテキストを創作しようとしたにしても、なんらかの根本史料が必要であったはずである。だから、実際に彼が記述の参考とするような記録が存在していたことは間違いない。それらを補綴するといった作業を彼が行っていたのも事実なのかもしれない。しかし、それと同時に、内容の編集と創作をも彼は行っていたのではないか。彼によって作り変えられた部分もあったろうし、それによって史実としての『甲陽軍鑑』の立脚点はかなり歪められてしまっている。そしてそれゆえに『甲陽軍鑑』は「史料として信用しがたい本」になってしまってもいるのである。
それでは、小幡が補綴し、基本資料として利用した書物、『石水寺物語』は、高坂弾正が書いたものであったと見てよいであろうか。
すでに指摘されていることは、『甲陽軍鑑』には戦国期に甲斐で用いられていた方言などが各所で使用されているということである。このことにより、『甲陽軍鑑』の基本資料として、戦国期に甲斐で記述された記録が用いられていたことはほぼ間違いないといえる。ただし、それは「戦国期に甲斐で書かれたものが用いられている」ということを証明してはくれても、それがイコール、高坂弾正が書いたものであるという証明にはならない。
先に述べたように、奥書の不自然さ、単純なミスの多さ、そもそも天正年間に高坂弾正は「高坂弾正」と名乗っていなかったという事実、などからすると、その基本資料は高坂弾正本人が書き残したものではないと見る方が自然ではないだろうか。むしろ『武功雑記』が伝えるように、「山本勘介の子で僧になっていたものが、高坂弾正の作と偽って書いた」といったことが案外、真実を伝えているのかもしれない。その辺は確信が持てないところであるが、『甲陽軍鑑』を高坂弾正が書いたことを承認するにはあまりにも疑問点が多すぎる。
ここまで述べてきた内容のポイントをまとめてみると次のようになる。
(1)『甲陽軍鑑』における上田原合戦、戸石崩れは、それが起こった年号や時季が史実とは異なっている。それは単なる記憶違いですまされるようなものではなく、意図的な改変によるものである。
(2)史実から改変された『甲陽軍鑑』の内容は、軍学テキストとして有用なものに作りかえられている。(特に山本勘介の記述を中心に)
(3)その作業を行ったのは軍学テキストとしてこの書を有効利用しようとした人物であろう。それは小幡景憲であった可能性が高い。
さらに言うならば
(4)『甲陽軍鑑』は、作者の記憶違いなどではなく、後世の創作の手が施された書物であり、これを基本史料として使用するのは不可能に近い。
といったこともいえそうである。もちろん、『甲陽軍鑑』が真実を伝えている場所もあるだろうから、内容によっては史料として使用できる可能性もあるかもしれないが、そのためには他の史料等によって裏付けをとることが必要であり、この書にしか載っていない内容をそのまま真実と捉えることははなはだ心もとない、ということである。
百歩譲って、『甲陽軍鑑』を書いたのが本当に高坂弾正であったとしても、その場合は彼自身が、内容を改変し書き換えているということになり、史料としての信憑性の欠如という事実は動くものではない。
最後に、07年度大河ドラマの主人公にもなっている山本勘介の実像とはどのようなものだったのであろうか。「市河文書」にその名前が出てくる通り、彼は実在の人物であり、武田晴信に仕え、それ相応の地位にもあった人物であったと思われる。
しかし、確実に分かるのはそこまでである。それ以上のことはまったく分からないといっていい。『甲陽軍鑑』において勘介は各所で大活躍を見せるが、「武田勢が危機に陥ったとき、軍師のようにすばらしい作戦を提案する」といった描かれ方そのものが、真実味を欠いている。何度も述べたように、彼に関する描写には、軍学を講義する際の手本として造形されているらしき側面があり、『甲陽軍鑑』に描かれている内容の多くが、創作であるに違いない。その点は、最初に紹介した『武功雑記』にある「吾親の勘介事を結構につくりかきたるなり」という部分が、ある程度の真実を吐露しているのかもしれない。真実を伝えている部分もあるのかもしれないが、それを実証する手立てがない。
『甲陽軍鑑』における勘介は、戦の際の作戦参謀としてだけではなく、城の築き方、馬出しの用い方などにもその才能を発揮している。実際に武田の城に丸馬出しが多く見られるという現象が、勘介の存在とリンクしているのかもしれないが、それを証明するものもない。
実際のところ、勘介がどのような人生をたどったのかもよく分からない。『甲陽軍鑑』の勘介は、永禄4年の川中島合戦において、その作戦を長尾政虎に見破られた挙句、その場において討ち死にしている。しかし、そのことすら真実であったかどうか証明するすべが無いのである。
現在、千曲川のほとりには山本勘介の墓というのが現存している。墓が実在しているからには勘介がそこに討ち死にしたことが間違いないようにも思われる。だがその墓は、明らかに中世のものとは思えないもので、現地案内板によるとこれは元文4年(1739)に、松代藩家老鎌原重栄によって建てられたものだとしている。すると、『甲陽軍鑑』がすでに世間に広まってからの建立であり、墓を建てた根拠が『甲陽軍鑑』だけであった可能性も無きにしも非ず、である。
勘介の実像がどのようであったか、結局のところ、その結論は想像の中にしか存在し得ないのである。