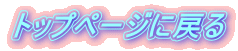
真里谷城をめぐる諸問題 04.3.12
*関連城郭 真里谷城 天神台城 要害城 大羽根城 岩室城 萱落城
天文6年、真里谷家の庶長子信隆と、嫡子信応との対立はピークに達し、すでに真里谷を追わていた信隆は、真里谷新地に城を築き、峰上、百首の2城と連携しながら、真里谷城の本宗家(信応)に攻撃を開始した。信隆には北条氏綱が荷担していたらしく、氏綱は金谷斎をリーダーとする特殊部隊を上総から真里谷新地城へと派遣した。天文2,3年の里見家の内乱で北条氏の援助を受けた里見義堯も、これを支持した。これらの城兵たちは、真里谷総領家を倒し、信隆をその座につけることを目途としていた。
一方、真里谷氏を支持基盤としていた小弓公方はこの対立を見過ごすことができるはずもない。彼は直ちに上総に派兵、そして新地、峰上、百首の3城を攻撃した。小弓公方の武力は圧倒的であったようで、これに圧倒された里見氏はあっけなく公方方に寝返ってしまい、結局下総、上総、安房の3国の兵に囲まれた3つの城の兵たちは降伏するしかなくなった。信隆は城を明け渡して、相模に避難、北条方の金谷斎も(いろいろあったようだか)赦免されて引き上げていった。このことにより、真里谷氏の内乱を終結させた小弓公方は後顧の憂いなく、翌年には国府台に進出、北条氏との決戦に挑むことになっていくのであった。
これらの事件の内容については、「快元僧都記」「氏綱書状(東慶寺文書)」などからおぼろげながらかいま見ることができる。
「快元僧都記」(原漢文なので書き下し文に直した)
「天文3年11月。
上総真里谷椎津城、相掛くる。大弓より御馬出さる。敵百余人討ち取らるの由、注進云々。天下兵乱、此の如し。
天文6年5月14日。
上総錯乱により、新地に楯籠る所の真里谷一族、惣領取り除くべき由申し上ぐるにより、大弓義明御進発。打ち過ぎて16日、峯上に向かう。御馬を寄せられ畢んぬ。
18日。房州味方の処、心替りして敵と成る。百首城、大弓様御威光を以て三ヶ国の兵、之を責めるべき由申す。之に拠りて三ヶ所の城衆、兵を加う。共に相違なく御帰り、尤もの由云々。
27日。上総峯上、房州百首の城兵、新地の者共、御免の由、仰せ出られ、御悦有り。」
「北条氏綱書状」
「御返事ニ候へ共、此後つかいかへりまいらせ候ほとに、一ふて申まいらせ候、まりやつしん地ニきんこくさい人しゅをこし候事も、しか〃〃としりまいらせ候ハす候、まりやつなんきのよし申こし候時ハ、人しゅこし候とハ申候へ共、たれ人ゆき候共、そんし候ハす候、これへまいり候てよくき〃まいらせ候ほとに、とても□ほうおんの事ニて候間、おなしくハこれをも御たすけ候て、以後やうにも御たて候へかなと申、御わひ事にて候、まへに申候ハす候御事ニて候ヘハ、もちろんふかくは申まいらせ候ハす候、此よしたれニても御ひろう候て可給候、あなかしく、
五月二十四日 ほうてううぢ綱(花押)
東慶寺
いふ侍者 (東慶寺文書)「戦国遺文142」
「北条氏綱書状」
「おって申上候、まりやつしん地ニきんこくさい人しゅををき候、とても後しゃ□□の事にて候ほとに、かの人□□□とにのけさせられ候てくた□□へく候、此よし御申候て可被下候、あなかしく、
五月二十四日 ほうてううぢ綱(花押)
東慶寺
いふ侍者 (東慶寺文書)「戦国遺文143」
これらの文書に示されている内容は冒頭に書いた通りである。
この話の中に出て来る真里谷城、峰上城、百首城などは皆、上総を代表する城であり、周知のものである。しかし「真里谷新地の城」だけがどこを指すのか、明確に指摘することはできない。
しかし、千葉城郭研究3号の「真里谷新地の城について」(小高氏)によって考察がなされ、この新地城が真里谷にある天神台城のことであるらしいということはほぼ確定したという観がある。実際天神台城は、急造の未完成の城といったものであり、その構造からしてもこの新地城にあてるのにふさわしい感じはする。しかし、この件については、なお気になることが2,3あるので、ここでそれを簡単にまとめてみたいと思う。
真里谷城については、以前から不思議に思っていることが2つあった。
1つには、なぜ、こんな集落から離れた山奥に城を築いたのかということ。この地域を押さえるための城であるならば、もっと集落から近いところに築きそうなものである。ましてや、真里谷城はもともと武田信長が、上総一国を掌握するために築いた城であるはずなのだから、こんな辺鄙な場所にあってもしょうがない。現在の真里谷城の地取りを見ると、真里谷城は要害性はいいが、城下集落との関係の薄い城であるような気がしてならない。
そしてもう1つが、真里谷城のある場所こそが「しんち」であるということである。地元の方のお話では、「現在では地番が割り振られているが、もともとこの城全体が「しんち」という字であった」ということである。「城郭体系」ではここに「真地」の字を宛てているが、これは「新地」と同じものだと見て良いだろう。つまり、真里谷城こそが「新地」という場所にある城なのである。このことは実証学的な見地からみるとすれば看過しえない事実であり、そうであるからこそ、大野氏も、現真里谷城を「新地の城」としたのであろう。
しかし、真里谷城を新地の城とするには、その遺構的な規模から、大きな矛盾点がある。「新地城」は、真里谷氏の内紛にともなって急造された城と考えられる。つまり臨時に取り立てられた城郭である。だが、真里谷城はもっとずっと手の込んだ城であり、天文6年の内乱に関してこれだけの城を急造することは不可能といっていいだろう。
真里谷城は一時的に取り立てられてそれ以降うち捨てられた城ではなく、戦国期の後半までは用いられていた城であると思う。その根拠を遺構的な側面から挙げると以下のようになる。
1.千畳敷入り口の、かなり深く切り込んだ見事な枡形状虎口。
2.千畳敷背後の、郭内からの高さが6mにも及ぶ高土塁。
3.3郭の南側下にある横堀。この先端は断崖となり、その手前の部分から下まで竪堀が組み合わされている。
4.4郭(市野々曲輪)の北側の大堀切。
5.この城全体の縄張りは、主郭部、2郭群、3郭群、4郭群とばらばらに存在しており、こうなった理由には地形的な要因も大きいと思うが、逐次、拡張されていったからではないだろうか。つまり、戦国後期まで、時代時代に合わせて城域が広げられていった結果であると想像できる。
このように真里谷城はかなり手の込んだ城郭であり、「急造の城」とはとても言えない。しかし、この城が地名の上からは「新地の城」であることも間違いない。「この新地は、先の史料に表れてくる新地とは違うものである」と切り捨ててしまえば、それはそれで問題はないのだが、どうもそこが引っかかってしまうのである。
そこで、仮に次のように考えてみたらどうであろうか。
真里谷氏の居城の歴史を概観すると、いくつかの時代に分けられる。
A.武田信長が、最初に取り立てた真里谷城。
B.その後歴代の真里谷氏の居城となり、天文3年、真里谷信隆を追い出してから信応の居城となっていた真里谷城。
C.小弓公方の滅亡後、信隆が総領となってからの真里谷城。
通説ではA=B=Cということになっている。つまり一貫して真里谷氏の本拠となっていたのが現真里谷城であるということである。まあ、普通はこう考えるのが当然であろう。この方程式が成立するからこそ、「新地の城」は「真里谷城に対峙し、しかも未完成である天神台城」という方程式も成立するのである。しかし、A=Bはそのままでよいとして、BとCは違うものである可能性はないだろうか。そう感じるようになったきっかけは「小弓御所様御討死御物語」の次の記述を見たことであった。
「真里谷八郎太郎信隆、一両年は浪人して、氏綱を頼みて、武蔵の国の傍、金澤に在宿して年月を送りしが、此の時(小弓公方が討ち死にした後)小船に乗り、五百余町の海上を一時に渡海して、(氏綱の)陣中へ馳せ参ず。上総の国の諸侍この由を聞くよりも、百騎二百騎引き連れて、「我も我も」と氏綱の旗本へ時を移さず馳せ来る。然れば、真里谷、三日も過ぎざるに五百騎になりにけり。年月は信隆を嫉みつる弟の八郎四郎、その外親類、同苗、家の子に至るまで、氏綱と氏康の太刀影に恐れて、総領信隆に悉く膝を折る。」
とある部分。この書物はいわゆる軍記物なので、その内容のすべてを信用することはできないと思われるのであるが、事件からそう遠くない時期に書かれていたものであると思われるので、ある程度の信憑性を認めてもよいかもしれない。またここに描かれている状況も、実態とかなりあっていると思うのである。小弓公方を滅ぼした北条氏の影響で、真里谷信隆は当主に復活することができたという。「笹子落ち草子」や「中尾落ち草子」などの記述も参考にするなら、天文12年頃には、真里谷信隆が総領の位置にあった。彼が総領家に復活したきっかけは、やはり、小弓公方の滅亡であったとみてよい。
真里谷信応が、信隆に対して圧倒的に有利であったのは、小弓公方という後ろ盾があったからであり、小弓公方が消滅し、北条の直接的な影響力が及んでくるとなると、信応単独で北条に対抗するのはそうとう厳しい状況になったと思われる。北条という後門の虎を従えている信隆を、膝を屈して受け入れざるを得なかったという状況は、実際にあったことと捉えてもよいであろう。
そこで次のことについて考えてみよう。
「北条家のバックアップを受けて真里谷当主として復活した信隆はどの城を居城としたであろうか」
信隆は信応らの一派とはずっと対立関係にあり、かれらが許しを乞うたからといって、仲良く同じ所に居住するとは思えない。信隆が入城したのは、信応らがいた城とは別の城であった方がよい。信隆、信応双方にとって、長年対立してきた相手と同居するのは危険であると感じたであろう。対立し、追い出し、追い出された関係の両者が、同じ城に住み続ける可能性は少ない。このようなことから考えてみると、結果として起こりうることは次の2点のいずれかである。
(あ).信隆は真里谷本城に入城し、信応らは別の城に移った。
(い).信隆は真里谷本城以外の別の城に入城し、信応らは真里谷本城にずっと居住し続けた。この場合、真里谷氏の本拠地は別の城に移った。つまり旧真里谷城から新真里谷城に総領家の城が移動したということになる。
そこで注目されるのが真里谷城の「新地」という地名である。もともと新地城は、総領家に対抗するための拠点として信隆派が取り立てた城であった。この城は信隆にとってはなじみのある城であり、そのように庶しい城を改修して入城したと言うことを想定することができる。真里谷城が、城下集落から離れた山奥に位置している理由もこれで説明が付く。もともと新地城は、「敵に対抗するために臨時に築いた防御性の強い城」ということから始まっている。城下集落よりも、「要害性」こそが重視された城であったのである。
このように、(い)のケースの場合においては、「新地の城」が新たに真里谷氏の本城となった、つまり新真里谷城がこの時点で誕生したと言うことになる。先ほどの方程式のB=Cにならないケースというのはこのことである。真里谷宗家の城こそが真里谷城であるとするならば、信隆が復活したことによって、新地城が真里谷城となった瞬間はまさにこの時であったと言えよう。
「真里谷系図」から信隆と信応の項目を抜き出してみる。
「信隆 幼名八郎太郎。妾腹長男。信応後見の間、真里谷城に住す。信応長ずるに及び、椎津城主と成る。天文二十辛亥年八月二日卒。信隆院殿祥山全吉大居士」
「信応 八郎五郎。嫡子。大多喜在城。真里谷城を兼ねて知る。真里谷基城を以って庶兄信隆を推し、これを守らしむ。永禄7年、鴻台一戦に武勇。同年11月卒。信応院殿源岳長源大居士」
天文3年7月に兄弟の父恕鑑入道が死亡した後、この二人による相続争いが起こったものと考えられる。先の「快元僧都記」にあった、天文3年11月の小弓公方による椎津城攻撃は、当時椎津城に移っていた信隆を攻撃したということで、系図の内容と符合する。続いて信応伝の「真里谷基城を以って庶兄信隆を推し、これを守らしむ」は、先に述べた、小弓公方滅亡後の、信隆惣領復帰を示しているのではないだろうか。先の仮定では、この時に信隆は新地城に入り、ここを新たな真里谷本城とした、ということになる。真里谷城と真里谷基城とを区別して書いているのには、信応がいた真里谷城と、新たに本城となった真里谷新地城とを区別しようとする意思が働いているからと考えておく。
ここでの仮定をまとめると次のようになる。
1.信隆派は真里谷城と離れた山奥に新地城を築き、総領家に対抗しようとしたが、小弓公方の攻撃により城は落城、信隆は上総から去っていった。
2.小弓公方の死後、北条氏のバックアップを得た信隆は再び真里谷に来る。そこで信応らの真里谷城とは別に、新地の城を改修してそこに移り住んだ。これ以降、新地城が総領家の城となり、真里谷城と呼ばれるようになる。
3.新真里谷城はそれから独自の発達を遂げていくこととなる。
次に以上の仮定からさらに想像を膨らませて、もともとの真里谷城はどこにあったか(あるべきであるのか)について考えてみよう。現在の馬来田駅から真里谷にかけては、かつて「真里窪宿」という大きな集落が存在していたという。「真里窪宿」は、天正年間、里見義頼の「加倍状」を与えられている。加倍状とは、要するに保護を認めるという書状のことであるが、つまり真里窪宿は里見義頼に保護を訴えることができるほどの宿であったということになる。これとほぼ同文の加倍状は横田宿にも発給されている。横田宿は中世上総地域でも有数の大集落であった。この横田宿と匹敵するかも知れないほどの集落が真里窪には存在していたのかも知れないのである。(千城研合宿で滝川氏より伺った話)
真里谷城を最初に築いたのは武田信長である。(鎌倉大草紙) 彼がこの地域に城を築いたのは、古河公方成氏の命により、上総地方を掌握するためであった。となれば、彼は本拠地を定めるに辺り、上総国を支配するのにふさわしい場所を選んだはずである。上総國国府は現在の市原市にあった。しかし、ここは、北西に偏りすぎており、上総国全体を掌握する場所としては今一歩である。もっと内陸部に入り、東部にもにらみを利かせることのできる場所が好ましいと言えるであろう。そこで選地されたのが長南と真里谷である。上総国内の各所に兵を出すことができ、宿も存在している場所、それがこの2ヶ所であったのだろう。
真里谷で掌握すべき宿とは、上記の真里窪宿であったと思われる。この場所を選んだのは、この宿とそこを通る道を押さえることの重要性を認識したが故であろう。単純に要害性の高い山が好きだったからこの地域に来たとは考えられない。となれば武田信長の築いた真里谷城は、この真里窪の集落と密接な関係になければならないのである。
真里窪の集落を押さえるために城を築くと言うことになればどの位置が最も理想的であろうか。現在ある真里谷3城のうちで選ぶならば、それは真里谷城ではなく、要害城か天神台城ということになるのではないだろうか。真里谷城はあまりにも奥に引き込みすぎているのである。実際に要害城の下には現在でも宿の地名が残っている。つまり要害城(あるいは天神台城)は城下集落と一体化した城郭であったのである。この城は一時的に取り立てられただけの城ではない。
しかし、天神台城は先に述べたとおりに未完成で急造の城という形態の城である。これは遺構の様子から見ても間違いないことと思われる。武田氏の本拠として使用されていた城であるならばこれほど未完成の部分が多いのはおかしいということになろう。となると、集落を押さえるために築かれた最初の真里谷城は、要害城こそふさわしいということになる。
だがこのことには大きな問題がある。現在見られる要害城の大規模かつ技巧的な遺構は、明らかに戦国末期(天正年間)のものとみるべきものである。つまり、現在見られる要害城は武田信長の築いた城ではない。それは当然のことである。
しかし、我々が城の遺構を見る場合、それは常にその終末期の状態でしか見ることはできない。城が順次拡張されていったとすれば、もともとの城の形態はすっかり、後の遺構の中に埋もれてしまっているのである。だから、最初の真里谷城が要害城の位置にあったとしても、その時代の遺構を認めることは難しいに違いない。あるいは武田信長の頃の城は、山上ではなく、谷戸部に築かれていたのかもしれない。上総地方の城にはよくあるパターンである。その場合は、要害城のある山の麓のいずれかの場所に置かれていたと言うことになる。妙泉寺は真里谷氏とゆかりのあった寺院であり、この周囲に土塁のようなものが見られる。この辺りに居館があったという想定も出てきてしかりである。
いずれにせよ、要害城を、その遺構の状態から、初期の真里谷城であると判別することは不可能である。しかし、このように集落との関係で想定していくと、最初の真里谷城が要害城のある位置あたりにあった可能性はある程度認められてもよいのではないだろうか。そして、その真里谷城に対して信隆方の築いた新地城が現真里谷城であったと仮定してみよう。真里谷本城を窺うために、信隆はどういう位置に新地城を築くことを考えるであろうか。要害城からは東南の尾根筋の奥に入ったところにあり、背後で援助してくれる峰上城と百首城とに比較的連絡が取りやすい所にある現真里谷城は、わりとふさわしい位置にあると考えることができるのである。
ではその場合、天神台城はどのように見ればよいであろうか。
天神台城はむしろ、要害城の付属物と考えるのがよいのかもしれない。この2つの城の間には道路が一本通っているだけである。要害城と天神台城の2つで、間の集落とこの道路とを両側から押さえるような位置関係になっているのである。宿の南側の尾根から攻め寄せようとする敵を防御するための砦として天神台城はプランされたのではないだろうか。天神台城の横矢の折れをともなった堀は南側の尾根筋の方に向かって明確に見られるのである。
だいぶ想像が膨らんできたが、要害城が出てきたついでに、最終的にこの城を、だれが現在のような城にしたのかについても考えてみよう。上記の通り、現在の要害城は、戦国末期に大勢力によって築かれたものであることは間違いないと思われる。
要害城はその遺構を見れば一目瞭然の通り、拠点的な城郭となるべく、大勢力によって築き上げられた城郭であるといえる。「大勢力の」ということになると、結局の所、この地域では北条か里見かの二者択一ということになってしまうのであるが、実際の所、いずれの勢力によって現在見られるような城となったと見るべきなのであろうか。
天正5年、北条と里見は和睦し、それ以降、真里谷地域は里見氏の領分となったと考えられる。もし、北条によるものとするなら、永禄から天正5年までのものと言うことになる。北条か、里見か、このそれぞれについて想像できることをまとめてみよう。
1.北条家が完成させた場合
天正初期までに北条家の勢力は上総において里見を圧倒しつつあり、その余勢を駆って築かれたと言うことになろう。北条家は椎津城、窪田城を拠点的な城郭として改修しており、原氏、高城氏などを「椎津番」「窪田番」として、交代で在番を勤めさせていたことが史料上から伺うことができる。要害城も里見に対する最前線として、在番の城として用いられていたであろうと言うことになる。
要害城の麓にある妙泉寺は真里谷氏によって開基されたものであるが、ここには北条氏の文書が残されており、住職のお話でも「この寺院は北条氏の加護を受けていた」という話であった。北条がある時期、この地域にいたことを示していると考えられる。
だが一方、こういうことも言える。北条氏が在番集を置いた城の場合、椎津、窪田城に限らず、牛久番、関宿番、厩橋番など、その史料が残されているケースが非常に多い。しかし、この要害城での在番に関する文書は見受けられない。この辺りをどう見るか。
2.里見氏が完成させた場合。
真里谷氏を追って上総を手中にした里見氏が、いつの頃が、ここに上総(特に真里谷・横田地域)を押さえるための拠点的な城郭を築いたと言うことになろう。天正5年以前の両者の国境がよく分からないのであるが、北の笹子城に「正木大膳の城」という伝承があり、それを事実であったと仮定すると、横田郷を支配するための城として笹子城に正木大膳を置き、背後の真里窪宿を支配するための拠点として、要害城を整備したと言うことになる。
また、天正5年以降、この地域は里見氏の領地として確定するので、いつかまた手切れになるかも知れない北条氏に備えて、この地に大城郭を置こうとしたと言うことになるであろう。
このうちのどちらを取るべきなのであろうか。どちらも決定的な根拠に欠けていて、断定することはできそうもない。ここで歯切れが悪くなってしまうのは、要害城の遺構が、その構造的な側面から、北条のものとも里見のものとも判断しにくい要素を含んでいるからなのである。
要害城の構造上の最大の特徴は、山上に穿たれた巨大な横堀である。主郭周囲でも、幅10m近くもある横堀が巡らされているし、北側の外郭部には、幅が20mはあるほどの深い三日月堀があり、しかもこの堀は三重になっていた。これは少なくとも、里見氏の城郭構造とは一致しないものである。
基本的に里見氏の城の特徴としていえることは、「分断」という要素である。尾根上に郭を配置し、その間の尾根を深い堀切で大胆に分断していく、そのような構造を取っているものが里見氏の城には多いと思う。しかし、要害城の三重の三日月堀はちょっと色合いが違う。この三重堀が置かれているところは、かなり尾根幅が広くなっているところなのである。「分断」ということを強く意識した場合、この部分よりもさらに北側の、尾根幅が狭くなっているところに堀切を入れた方がはるかにてっとり早い。その方が少ない労力で、より有効な「分断」を図ることができるはずなのに、そういうことはせずに、尾根幅の広いところにあえて三重堀をおいている。これは、地形的にそうなったというよりも、この「三重堀」のような構造のものを造りたいというプランがあったと見る方が正しいであろう。つまり、三重の三日月堀を構造に取り込みたいという発想である。このような発想が里見氏にあったであろうか。そこが非常に悩ましい点である。
里見氏の山城で、大規模な横堀を巡らせているケースは極めてまれである。しいていえば、千本城に見られるくらいのものであろうか。遺構的な側面から里見氏と結びつけるのはなかなか難しいのである。
では翻って、これらを北条氏の築城技術と見るべきか。しかし、このことも断定できない。三重の三日月堀のようなものを持った城を私は知らない。(あるのかもしれないが) 少なくとも下総・上総で北条氏が関係したと思われる城の中には見あたらないのである。
三日月堀といえば武田氏(甲斐)を思い出す。真里谷氏も同じ武田氏であるとはいえ、これと結びつけるのはあまりにも無理であろう。真里谷氏に関連した城郭の中にも、似たような構造を見いだすことはできない。
ただ、小規模ながらも同じ上総地域で三日月堀が見られる城は、他に、岩室城(君津)、萱落城(大原町)などがある。このうち岩室城は不確定ながら、北条氏が久留里城を攻めるための向城として築いたという想定がなされている。つまり、北条式の城である。萱落城についてはその歴史は全く不明である。しかし、この地域は、万木土岐氏の勢力圏内であり、永禄期以降、土岐氏が北条方についていたことから、北条流の築城術が導入されている可能性はないとは言えないであろう。(しかし、この2つの城郭との関連性だけでは根拠としては心もとない気がしないでもない。)
もっと大まかに想像すれば、大規模な横堀を回すという構造は、里見氏よりも北条氏の城郭によく見られる構造ということができるであろうか。また、横堀といえば下総の大須賀氏関連の城郭でもよく見られる。下総の大須賀氏はやはり北条氏に属して、あちこちの城を在番をさせられているから、大須賀氏による横堀城郭は、北条氏のいずれかの城の構造を参考にしてできあがったものと考えるむきもあるであろう。このように考えると、要害城のプランは、きわめておおまかに、里見よりは北条っぽい、ということができるかも知れない。
しかし、要害城の堀は、この地域の城郭では他に類を見ない大規模なもので、これだけのものが造られるのは戦国最末期ではないかとみるむきもあるかもしれない。もし、この遺構を天正5年よりも後のものというように想定するならば、選択肢は必然的に里見しかなくなってしまう。
もう1つ、小田原の役以降、この地に入部してきた徳川家臣のいずれかが要害城を改修していたという可能性も残されているかもしれない。ただ、その場合、そのことを示す史料なり伝承なりが残っていてしかるべきであると思うが、そのようなものは何もない。
さらに里見と北条とに関していえば、現真里谷城の東南3kmという、わりと近い位置にある大羽根城との関連性が気になる。大羽根城は養老川沿岸に築かれた比較的規模の大きな山城である。この城に関しては次のような伝承が地元には残っている。
「大羽根城は天正年間に里見氏が千葉氏に備えて築いた」
天正年間に里見氏がここに城を築くのはよいとしても、それが千葉氏に対してだということには違和感がある。この地域には「里見」の地名が残っていることもあり、里見氏がある程度の影響力を及ぼしていたことは間違いない。しかし、天正年間に里見氏が対峙していたとしたら、それは千葉氏ではなく、北条氏であろう。だが、よくよく考えてみよう。北条氏が里見氏と対峙していたからといって、直接、北条氏の一族がこの地域に来ていたとは限らない。天正期には北条氏は、椎津城番(市原市)や久保田城番(袖ヶ浦市)として、千葉配下の原氏や高城氏などを派遣している。これらの千葉一族が、当地域にも進出してきて、里見氏と対峙していた、この想定ならば起こりうると言える。つまり、「里見氏と千葉氏が対峙していた」ということを「里見氏と北条配下の千葉一族とが対峙していた」というように読み変えれば、千葉氏に備えてという伝承もあながち誤りではないのである。しかし、実体としては、里見氏が北条氏に備えてこの城を築いたとした方が遙かにわかりやすい。
当の大羽根城であるが、これは城郭の縄張りから見て明らかに里見系の城郭としてよい城である。山稜を堀切によって何段にも分断して直線漣郭式の構造を取っている構造はまさに里見系城郭の特徴で、殊に南側の尾根続きにある5連続堀切は、峰上城の7つ堀切と近似している。里見氏が天正期に築いた城であるという伝承は、遺構の上からも証明できると考えてよいだろう。
もし、里見氏が大羽根城のような城をこの地域に築く必要があるとすれば、裏を返して言えば天正年間にこの地域に北条氏の拠点が存在していたからということになるであろう。天正年間に北条氏が拠点としたかも知れない城郭をこの地域であげるとすると、その候補は極めて限られてくる。もちろん候補の筆頭となるのは要害城であろう。この仮定を立脚点とするならば、天正年間にこの地域で里見と北条とが対峙しており、
里見=大羽根城
北条=要害城
というように2つの城が境目の城として機能していたというように考えられるであろう。
ところでこの時、真里谷城はどうなっていたのであろうか。真里谷城がいつまで使用されていたのという点についてはよく分からない。真里谷氏そのものは、天文末年間までにこの地域から追われていた可能性がある。しかし、最初に述べているように、真里谷城はその後もこの地域における要害として、いずれかの勢力によって利用されていた可能性は高いと思う。とはいえ、それを里見と見るべきか北条と見るべきか、具体的なことについては想定する材料に欠けている。しかし、北条と里見がこの地域で対峙する時期には、いずれかが要害として利用する価値は十分にあったかと思われる。
以上、真里谷城が「新地」にあることから想像をたくましくして、あれこれと述べてきた。しかし、こうして述べてきたことも全ては推定の産物にすぎず、状況証拠以外の具体的な根拠には欠けている。第一次国府台合戦の後の真里谷信隆は、結局真里谷城に入ることはできず、ずっと椎津城あたりを居城としていたかもしれないのである。
ただ、真里谷城と新地城の特定に当たってはまだまださまざまな推測の余地があるのではないか、ここで述べたいのは結局はそういうことなのである。