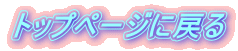
「信長公記」に見る桶狭間の真実とは
有名な桶狭間合戦の実相については、かつては、小瀬甫庵の「信長記」をベースとして帝国陸軍参謀本部が編集した説が 一般に流布していた。信長は窪地に陣取った今川義元を背後の山から攻め込んで討ち取ったというような、以前はよく言われていた話である。大軍をうち破る時の模範的な戦法として、それがかつては語られ続けてきた。
が、近年、山の背後をまわったとか、裏手から攻撃したというようなことは言われなくなってきている。それというのも、信長の伝記の中では最も信頼できると言われている「信長公記」の内容が注目され、その内容に沿った状況が説明されるようになってきたからである。「信長公記」の内容に従えば、信長は、「桶狭間山」に陣取った今川義元に対して、真っ正面から突っ込んでいったことになっている。迂回することもなければ、裏山から窪地の義元を見下ろすこともなく、ただ、ひたすら一直線に桶狭間山を目指して進軍しているのである。
しかし、実際のところ、「信長公記」にはまだまだ多くの謎がある。「信長公記」の記事を再検討してみると、さらにそこに隠された秘密があるのではないかと思われる節がある。本稿は「信長公記」の作者、太田牛一が、どういう意図を持って桶狭間合戦の部分を執筆したのかを検討してみるものである。原典としては新人物往来社から出ている「信長公記」(町田家伝来「信長公記」完本をベースとして、太田牛一自筆本とされる前田家本「元禄十一年記」を参照し交合したもの)を用いている。
まず、信長が家督を相続してから、桶狭間合戦にいたるまでの事象を通説によってまとめてみる。
天文20年(1551) 信長の父信秀死亡。家督を相続。(信秀没年については他にもいくつか説あり)
天文21年(1552) 清洲城の坂井大膳らと戦う。
弘治元年(1555) 守護代織田彦五郎を倒し、清洲城を奪取。
弘治2年 (1556) 信長の弟勘十郎信行、林美作、柴田勝家らとともに信長にそむくが、敗れる。
永禄2年 (1559) 岩倉城の織田信安を追放。尾張一国統一を成し遂げる。
永禄3年 (1560) 桶狭間で今川義元を討ち取る。
永禄4年 (1561) 西美濃に攻め込む。(十四条合戦) 墨俣要害を構築。
永禄10年(1567) 美濃を攻略。
以下の内容を把握するために、この流れをざっと頭に入れておいていただきたい。
さて。桶狭間合戦には不思議な点がいくつかある。まず一点目は、双方の兵数である。「信長公記」では次のようになっている。
織田軍 決戦時 2000足らず
今川軍 桶狭間で 45000
これで見ると今川軍は織田軍の実に22.5倍という兵力である。これだけの兵力差があって、果たして本当に戦闘が可能なのであろうか。よしんば奇襲が行われたとしても、大将を討ち取るなどと言うことができるのだろうか。しかも、「信長公記」では、信長は桶狭間の西手の中島砦から、水田中の一本道を真正面から突っ込んでいったということになっている。いくら信長とてもこの状況で今川本陣を打ち破るのは難しすぎるであろう。参謀本部編の、裏手に回って背後から奇襲したという解釈も、その点に矛盾を感じたことから生じたものなのであろうと思われる。
軍記物の記述で、双方の兵力については味方を少な目に、敵を多めに書くという傾向がある。この兵力差にも、実はそうしたフィルターがかけられているのではないだろうか。つまり実際の今川軍はもっと少なく、逆に織田軍はもっと多かったのではないか。
ところで、今川軍と織田軍の当時の領地から見て、両軍の動員可能兵力はどの程度に見積もれるだろう。動員可能な兵力は、主に領土の石高の多寡によって決まる。慶長3年(1598)の検地帳(太閤検地)からだいたいの石高を計算してみよう。
今川 駿河 150000石
遠江 255160石
三河 290715石 計695876石
織田 尾張(信長は前年に尾張統一を果たしている) 571737石
駿河、遠江に加えて松平領であった三河までをも加えた今川対、尾張一国しかない織田とでは、かなりの領土の差があったかのような印象を受けるのだが、尾張は非常に豊かな国であり、石高の差で見ると、実はこのように10対8くらいの割合でしかない。
さて、大名の動員可能兵力の目安として、一万石あたり300人ほどという計算の仕方が一般に行われている。あくまでも目安であるが、この石高によって双方の動員可能兵力を割り出してみると、
今川 20850人程度
織田 17150人程度
確かに今川軍の方が動員可能兵力が多いが、従来言われていたような圧倒的な差ではない。さらに、今川軍とても全軍を率いて戦いに赴くのではない。今川の領土の東には北条氏が、北には武田氏がいる。当時同盟関係が成立していたと仮定しても、戦国の世である。それらに対しての備えの兵を残しておかなければならない。要所要所の城には、100人200人と兵を配置しておく必要があるだろうし、本拠地の駿府にもまとまった兵力を残しておかないわけにはいかない。従って、実際に今川が動員できた兵力は20000人から何割かを差し引いた数であったはずである。そこで国元に残しておく兵をかなり少なく見積もって仮に2割の4000人とすると、尾張に連れていける兵は16000人内外ということになる。しかも、そのうちの4割近くは三河兵である。(今川の領土の内の4割の300000石近くが、新地の三河なのである)三河は元々松平氏の領分であり、今川義元は松平広忠の忘れ形見元康(後の徳川家康)を人質とすることで、自分の分国のようにしていた。三河兵は、もともと今川の家臣ではなかったから、今川に対する忠誠心も劣るであろうし(逆に元康を人質に取られていたことで反発を感じていたかもしれない)動員可能な兵力をすべて出すとも思えない。と言うことになると、今川の兵力はさらに少ないものだったということにもなる。
それに対して、織田軍の方も、17000人が手放しで動員できたとは思えない。尾張の国境付近をかなり今川勢に浸食されていた気配はあるし、服部右京助が今川に内通して敵対行動をしていたということもある。支配して一年にしかならない上四郡がどの程度信長に服属していたのかもはっきりしない。しかし、尾張の国力を量るのにはもう1つ重要な要素がある。尾張はもともと商業の盛んな地で、信長も、後に楽市楽座を行うなど、商業に力を入れていたことが知られている。
「信長公記」には、信長と斉藤道三が天文18,19年頃の4月下旬、美濃との国境付近、富田の正徳寺で面会したとき、信長の率いてきた軍に対して次のような描写がある。
「三間々中柄の朱やり五百本ばかり、弓、鉄砲五百挺もたせられ・・・」
信長が鉄砲に早くから注目していた武将であることはよく知られているが、この当時にして、信長は数百挺の鉄砲を持っていたらしいのである。本によっては「鉄砲五百挺」と解釈しているのもあるが、「信長公記」では「弓、鉄砲五百挺」とある。弓と合わせてなのだから実際には200挺、あるいは100挺程度だったのかもしれない。しかし仮に100挺だったとしても、ポルトガル人が種子島に漂着して鉄砲を伝えたのは天文12年(1543)のこと。それからわずかに6,7年後には100挺もの鉄砲を持っていたことになる。鉄砲はこの当時まだ相当珍しいものであったはずであり、おそらく一挺の鉄砲でも、現在の新兵器がそうであるように、数百万、数千万もするような高価なものであったであろう。にもかかわらず、この前後の記述にも「(信長は毎朝)鉄砲御稽古、師匠者橋本一巴にて候」(天沢長老物かたりの事)「鉄砲取りかへ取りかへ放させられ」(村木の取出攻められしの事)といった表現が見られ、信長はかなり早い時期からこのように高価な鉄砲を活用していたことがわかる。
種子島に伝来した鉄砲の仕組みを手先の器用な日本人が解明して生産が始まっていたとしても、そう流通が進んでいたとは考えられないし、その真価が分からず、購入をためらっていた大名も多かったであろう。にもかかわらず、これだけの鉄砲を持ち活用していたと言うことから、その先見性とともに、当時から信長がかなり豊かであったと言うことが想像されるのである。後の楽市楽座政策などを見ても、信長がかなり商業的な感覚に優れていたことがわかる。そういう感覚が身に付く環境に彼がいたと言うことは、国内に商業的に豊かな状況があったのである。
また、鉄砲購入には堺の商人との交渉も必要であろう。彼らとのつながりもあったはずである。このように、信長の勢力を推し量るには、石高と同様、商業面での収益も考えねばならず、それらをも含めてみると、今川との力の差は実質的にほとんどなかったものとも言っても過言ではないかもしれない。
さて、信長の父信秀は、尾張半国の兵を率いては各地で戦をしている。織田信秀は、清洲尾張家を差配する部将としての力を蓄えているのだが、実体は、尾張の下4郡を支配していた清洲織田家のそのまた家老でしかなかった。清洲織田家を倒し、さらには岩倉織田家をも倒して尾張統一を果たすのは、信長が跡を継いでからのことである。「信長公記」の巻頭には次のように記述されている。
「尾張国は八郡なり。上の郡四郡、織田伊勢守諸将手に付け、進退して岩倉と云ふところに居城なり。半国下の郡四郡、織田大和守が下知に随へ、上下、川を隔て、清洲の城に武衛様を置き申し、大和守も城中に候て、守り立て申すなり。大和守内に三奉行これあり。織田因幡守、織田藤左衛門、織田弾正忠、この三人、奉行人なり。」
このようにもともと三奉行の一人にしかすぎなかった織田弾正忠信秀だったが、かなりのやり手だったのであろう。彼は着々と勢力を蓄え、尾張半国の兵を総動員できる実力者になっていく。次の「あづき坂合戦の事」の項では、三河国安城に侵攻してきた今川の兵と闘い、これを防いでいる。
この織田信秀の動員兵力はどの程度のものだったのであろう。
織田信秀が美濃に討ち入り大敗を喫した記事が「信長公記」に見えるが、この時「歴々五千ばかり討ち死になり」とある。信秀がどの程度の兵を率いていったのかははっきりしないし、五千という数も眉唾な気がするが、五千討ち死にというからには五千よりもかなり多い兵を率いていたのは間違いないだろう。尾張半国を仮に30万石とすれば、動員可能兵力は単純計算で九千人と言うことになる。ちなみに信長関係の記事を集大成した「総見記」(江戸時代成立)では、この時の信秀の兵力を「一萬余人」としている。そうすると、石高から見た信秀の勢力とほぼ一致することがわかる。
また、これより少し前、天文17年(1548)駿河の今川義元と合戦したという記事がある。(織田と今川義元との合戦は桶狭間以前にも何度か行われていたのである。)再び「総見記」の記事を見てみると織田信秀は「自身八千の人数を率ゐ」となっている。この戦いは結局どちらの勝利になったのかはよくわからない合戦なのだが、とにかく信秀には八千(やはり石高から割り出した九千にかなり近い数値である)の兵を率いるだけの実力があったと見てよいだろう。(もっとも、この時期信秀は三河安城城を所有しており、三河にも勢力を侵犯させていたことがわかり、三河で味方にした兵力も含まれているのかもしれない。今川の侵攻はこうした織田の動きに対するものであろう。)
繰り返すようだが、当時の織田信秀は、尾張の南半国を支配していた清洲織田家の家老でしかなかった。それでいて、これだけの兵を率いて合戦に臨むだけの実力があったのである。永禄3年(1560)時点での信長の勢力は、尾張半国などといった程度のものではない。信長は桶狭間合戦の前年である永禄2年に岩倉織田家を降して、尾張一国の統一を成し遂げた。(「浮野合戦の事」「岩倉落城の事」)これは父信秀にも果たせなかった偉業である。先に述べたように、尾張一国は57万石、ここから割り出せる兵力は1万7千人あまり、しかも信長の経済的な実力をも加算したら、信長は2万程度の兵を動かすだけの実力者であったといえよう。
それなのに、なぜ信長は桶狭間に二千人しか動員しなかったのであろうか?この二千人足らずという「信長公記」の記述は真実なのであろうか。実は、その謎を解く手がかりは当の「信長公記」の中に隠されているともいえる。
「信長公記」は信長の伝記の中で最も信憑性が高いものだといわれている。「信長公記」の作者である大田和泉守牛一は若い頃から足軽大将として信長に仕えた武士であった。桶狭間にも彼は実際に出陣している可能性もある。それなのに、彼は「桶狭間」の記述について大きなミスを犯している。
桶狭間合戦は永禄3年(1560)5月19日に行われた。どの歴史の本を見てもそう書いてある。ところが最も信憑性が高いはずのこの「信長公記」では、永禄3年にはなっていないのである。「信長公記」は、この合戦を天文21年(1552)のこととしている。この年号は明らかに間違っている。桶狭間合戦が永禄3年にあったことは他のあらゆる史料から見ても疑いようがない。大田牛一はなぜ、8年も前の年号を記しているのだろうか。従来、この年号の疑問については、さまざまな人から指摘されてきた。が、結論としては、大田牛一の単なる勘違いという解釈だけで片付けられてきた。だが、本当にこれはただの勘違いだったのであろうか。この誤った年号が具体的にどのように記述されているのか、「信長公記」の本文を見てみよう。
「信長公記」では、「鳴海の城へ御取出の事」の次に「今川義元討死の事」という項目があり、その始めに「天文21年壬子5月17日」という年号を掲げ、今川義元が沓掛へ参陣してきたことを述べている。18日夜、信長はろくな戦略も言い出さないまま、家臣たちを帰してしまう。しかしその夜、彼はいきなり出陣するのである。熱田神宮に参詣し、陣を整えたあと今川軍の様子を伺うと「御敵今川義元は、4万5千引率し、おけはざま山に人馬の休息これあり」という。そしてその直後に「天文21年壬子5月19日」という記述をまたもやしている。そして、信長が軍勢を集めていよいよ今川本陣にかかる場面で3たび「天文21年5月19日」と述べている。つまり、この桶狭間の項目だけで、天文21年という記述を念入りに3回も繰り返しているのである。これを単純に記述ミスと言い切ってよいものだろうか。3回まで同じ年号を繰り返しているのには、何かもっと別の意図があったのではないだろうか。
ところで「信長公記」は、この桶狭間の部分で見られるように、年号を念入りに記述するということを普通に行っている本なのであろうか。「信長公記」の巻首は、信長が足利義昭とともに上洛するまでの出来事を記述したもので、かなり大部になっている。「信長公記」16巻のうち、全体の6分の1の分量を占めている。そこにはさまざまな記述が見られるが、実は年号を示している記述は非常に少ない。年号が挙げられているのは次の事件に際してのみである。
三の山赤塚合戦のこと・・・・・天文2年癸丑4月17日
林美作の乱・・・・・・・・・・弘治2年丙辰8月24日
桶狭間合戦・・・・・・・・・・天文21年壬子(3回出てくる)
織田勘十郎の御生害・・・・・・弘治4年戊午霜月2日
十四条合戦のこと・・・・・・・永禄4年辛酉5月上旬
これらの7回のみである。巻首の45項目の記事に対し、4つの項目でしか年号を記していない。巻首には、信長の元服、信秀の死、斉藤道三との会見、守部合戦、稲葉山城乗っ取り、上洛等々印象的な記事がたくさんあるのに、そういった記事にも年号が描かれていない。しかもそのうちの3回が桶狭間の年号である。
こうした書き方から見るに、もともと「信長公記」の巻首は、年号をそれほどきちんと記述しようと意識して書かれてはいなかったと考えられる。そのような記述方法を取っていながら、桶狭間でのみ3度も同じ年号を繰り返す。新人物往来社「信長公記」で、巻首60ページ分に7回しか出ていない年号のうちの3回が「桶狭間」の4ページ分に出ているのである。これだけ繰り返しているというのは、それだけこの年号を太田牛一は強調したかったからであろう。これは、牛一の勘違いといったものではない。彼は確信的に、あるいは何らかの意図をもって、あえて桶狭間合戦を天文21年に起こった出来事と主張しているのである。
さて、桶狭間前後の信長の事績をまとめると実際は次のようであった。
1.
信長の父が死ぬ。
2 林美作が信長の弟勘十郎信行を担いで謀反を起こす。
3 弟勘十郎信行を自殺させる。
4. 尾張一国を統一する。
5. 桶狭間合戦。
6. 美濃を乗っ取る。
しかし、「信長公記」の記述の順序は次のようになっている。
1. 信長の父が死ぬ。
2. 林美作が信長の弟勘十郎信行を担いで謀反を起こす。
3. 桶狭間合戦。
4. 弟勘十郎信行を自殺させる。
5. 尾張一国を統一する。
6. 美濃を乗っ取る。
人間の記憶というものはあいまいなもので、そのことが起きた年号をだいぶ後になってからも正確に覚えているのはとても難しいものである。しかし、一連の印象的な出来事については、年号はともかくとして、その順序は話の流れとして、正しく覚えていることが多い。桶狭間については、信長が跡をついでからすぐの出来事ではなく、尾張一国が成し遂げられた次の年の出来事であった。(ということは、今川義元の侵攻も、尾張一国を成し遂げた信長に脅威を感じたことが直接の原因であったのであろう)しかし、「信長公記」では桶狭間合戦を信長が跡をついですぐの事とし、その後に、信長は尾張統一を成し遂げたという順序になっている。このような誤りを、現実に信長に近侍していた人物が犯すであろうか。先ほどの、同じ年号を3度繰り返していたことといい、これにはやはり何か意図的なものを感じるのである。大田牛一は、誤りなどではなく、何らかの意図を持って、桶狭間合戦をあえて、信長が父の後をついた直後の位置に持って来ようとしているのである。
ところで、大田牛一が書く「天文21年」当時の信長の勢力はどのくらいであったろうか。
信長のそのころの勢力は、「信長公記」の「今川義元討死の事」の4つほど前の項目「おどり御張行の事」の末尾に記されている。それによると、
「上総介信長、尾張国半国は御進退なすべき事に候へども、河内一郡は、二の江の坊主服部右京進押領して、御手に属せず。知多郡は駿河より乱入し、残って二郡の内も、乱世の事に候間、慥かんい御手に随わず、此の式に候間、万御不如意千万なり」とある。
つまり天文20年頃の信長の勢力は、尾張下4郡のうちのわずか二郡、その二郡も反乱者が多くてままならないという状況だったということである。尾張下4郡郡を、尾張の半分とすれば、約38万石。そのうちの2郡ということになればまた半分の190000石。動因勢力は6000人弱ということになる。このうちでも反乱者が絶えなかったということなのだから、実際に動員できるのはそれから何割か引いた数であろう。仮に3割ほど引いて4000としてみよう。さらに各所の城に兵を配備する必要もあるだろうから、決戦に動員できる兵力はさらにその半分、2000程度ということになる。となると、「信長公記」に描かれている兵力数に近い数字ということになる。つまり「信長公記」は桶狭間合戦をあくまでも天文21年のこととして描いているために、信長の兵力も天文21年時点(尾張統一前)のものとして表現しているということになる。
桶狭間での信長の言動にも、彼が少数の兵しか持っていなかったとはとうてい思われないものが見られる。今川軍に攻撃をかけようとする信長は次のように言っている。
「各々よく々承り候へ。あの武者、宵に兵糧つかひて、夜もすがら来たり、大高へ兵糧を入れ、鷲津・丸根にて手を砕き、辛労してつかれたる武者なり。こなたは新手なり。その上、小軍なりとも大敵を怖る〃なかれ。運は天にあり。此の語は知らざるや、懸からばひけ、しりぞかば引き付くべし。是非に於いては、稠(おお)ひ倒し、追い崩すべきこと、案の内なり」
ここでまず考えねばならないのは、この会話の前半部分である。信長は、今川の「本陣」を狙い撃ちするのだとは言っていない。むしろ、とりあえず、先陣を叩こうという気構えである。というのも、この少し前の部分に次のような部分があるからである。
「今度家康は朱武者にて先懸をせられて、大高へ兵糧入れ、鷲津・丸根にて手を砕き、御辛労されたるに依つて・・・」
大高へ兵糧を入れて、鷲津・丸根で手を砕き、辛労しているのは先陣の家康の軍であると「信長公記」ははっきりと言いきっている。つまり今信長が叩こうとしているのは、鷲津・丸根で疲れきった家康の軍なのである。(と信長は認識していた) 疲れた先陣を叩いて勢いをつけるというのは戦法としてはまずくはない。しかしそれは、当方にもそれなりの兵力がある場合の話である。敵の十分の一しかない兵力で、このような戦法を立てるのは狂気の沙汰であるとしか思えない。
しかも、さらに信長はこう続ける「懸からばひけ、しりぞかば引き付くべし・・・・」これも戦術的には間違ってはいない。敵と戦いながら、わざと引いて見せ、敵が調子に乗って追いかけてきたところを、伏兵が襲い、敵を混乱させやがて壊滅させる。このような戦法は、古来多くの武将が用いている。ある意味では常套的な戦術の1つともいえる。しかし、これも、彼我の軍勢が拮抗している場合でなければ不可能な戦術である。敵の十分の一しかないわずかな兵力で、懸かって引いたならば、敵の大軍が勢いに乗って攻め寄せ、たちどころに味方は壊滅してしまうのは目に見えている。敵と拮抗できるだけの兵力がなければ、とても言えないはずのセリフである。
また、信長軍の進行ルートは、今川本隊に気づかれないように敵の背後を回るなどという技巧的なものではなく、熱田神宮→丹下砦→善照寺砦→中島砦→桶狭間と一直線に進軍している。敵に迫る最短ルートであるが、敵に自の軍勢が少ないことを正面から見られても気にしないという構えである。
さらに桶狭間合戦翌日の「頸実検」の描写では、「頸数三千余あり」とある。この数字には誇張があると思われるが、2000の兵力で3000余の首を取るというは、多すぎであろう。だいたい、頸は打ち捨てにするというのが奇襲戦での定法であるはずである。3000とまでは行かなくとも、これに近いような人数を討ち取っていたとしたら、信長の兵力は2000程度ではありえないということになるだろう。
これらの言動は信長軍が真実2000しかいなかったとしたら、大きな矛盾となる。今川勢45000に対して2000では、とうてい取ることのできないはずの言動なのである。ここで、発想を転換させて、織田軍は従来言われているように寡勢力ではなく、今川ほどではないにせよ、拮抗できるだけのそこそこの兵力を持っていたと考えてみたらどうであろうか。実際のところ、そう考えるだけで、これらの矛盾はすべて解決する。
中島砦に進軍する信長軍を「信長公記」は「此の時、二千に足らざる御人数の由、申し候」と言っている。大田牛一は、他の部分ではだいたい断定的に述べているのに、この部分での「申し候」という自信のない表現はどうしたことであろう。こういう表現は「信長公記」であまり見られない。「申し候」は誰が誰に申したのかも、はっきりしない。
しかし、こういう反論もあるかもしれない。「信長は前日の軍法会議で何の戦略も説明せず家臣たちを帰している。大軍を率いるのならば、この行動はおかしいのではないか」
だが、おかしいとも言い切れない。信長の行動は電光石火のごとく素早く進軍することにあり、これは彼の生涯を通じて基本的なあり方の1つであった。たとえば、朝倉攻めをする時も、京で兵揃えをするという名目で、のんびり京に集合すると見せかけ、突然矛先を変え、越前に向かってダッシュをかけている。桶狭間の前日も、彼には出陣の意志が固まっていたのだろうが、出陣するまさに直前まで、そのことは伏せておこうとしたのだろう。信長の周囲にも今川の間者がいるかもしれないということを恐れるが故である。
これまで述べたところを整理すると、
1.「信長公記」は桶狭間合戦を天文21年(1552)のこととしている。(永禄3年の8年前)
2.天文21年段階の信長は亡父の跡を次いで間もなく、自在に使える兵力は2000程度のものであった。
一方で、
1.実際の桶狭間合戦は永禄3年(1560)である。
2.この前年に信長は尾張統一を果たしており、この時点での信長の動員兵力ははるかに大きくなっており、1万7千人程度あった可能性もある。
そして
1.「信長公記」は信長の桶狭間での動員兵力をあくまでも天文21年時点のものとして書いている。
2.「信長公記」の内容は、一方では信長の兵を2千人足らずとし、当方の兵力が少ないという表現を何ヶ所かでしているにもかかわらず、信長の言動は、信長の兵力がそこそこあったことを示している。
ということになる。
信長の伝記としては太田牛一の「信長公記」とほぼ同じ頃に成立した小瀬甫庵の「信長記」がある。(太田牛一のも本来「信長記」なのだが・・・。)太田牛一とは異なり、桶狭間合戦よりも以降に生まれた甫庵は、信長の若い頃の伝記を自身の記憶によって書くことはできず、牛一の「信長公記」などをよりどころとして書いていったことであろう。その際甫庵は、2000余りの兵力で、正面攻撃をかけて今川の本軍をたたくという内容が、現実的にあり得ないことだと考えたのであろう。小人数で奇襲を成功させるためには、裏手に回って、背後から襲う以外にはないのではないか。彼はそう考えて、牛一の桶狭間の内容を自分の「信長記」では書き換えた。その甫庵本の「信長記」が、近世以降世上に流布したがために、桶狭間の裏手からの奇襲が、かつては史実として解釈されてきたのである。
さて、先に「信長公記」巻首で年号がついているものの一覧を挙げておいた。これをもう一度確認してみよう。
三の山赤塚合戦のこと・・・・・天文2年癸丑(1533)4月17日
林美作の乱・・・・・・・・・・弘治2年丙辰(1557)8月24日
桶狭間合戦・・・・・・・・・・天文21年壬子(1552)(3回出てくる)
織田勘十郎の御生害・・・・・・弘治4年戊午(1558)霜月2日
十四条合戦のこと・・・・・・・永禄4年辛酉(1560)5月上旬
この中で、通説と年号があっているのは「林美作の乱」、「十四条合戦のこと」、「織田勘十郎の御生害」の3つである。この3つについては干支も正しくなっている。ところが「赤塚合戦」は干支が合っていない。これらについて少し考えてみよう。
*「赤塚合戦のこと」・・・・・「信長公記」のいう天文2年では、天文3(1534)生まれの信長はまだ出生していないことになってしまう。また天文2年の干支は実際は癸巳で、干支もあっていない。では、この近辺で干支が癸丑になっているのはいつかと見てみると、天文22年なのである。このことから想像すると、「天文2年癸丑4月17日の赤塚合戦」は、実際には「天文22年癸丑4月17日の赤塚合戦」の誤記である可能性が強いと思われる。「総見記」巻2の巻頭には「山口左馬助謀叛事同尾州赤塚軍事」の項があるが、この内容をまとめると
・この軍が起こったのは天文22年癸丑4月17日
・山口左馬助親子が謀叛を起こしたことが原因。
・信長はわずか19歳ながら800の兵を率いて鳴海表に出陣。
・敵は1500余り。
・勝敗は不明。
となる。詳細はわからないことも多いが、天文22年頃、信長が800の兵を率いて桶狭間に近い鳴海に出陣し、山口氏の2000余りの兵と戦った事実はあるらしい。少数の兵力で同じような場所に出陣していることの類似から、この辺りに桶狭間を押し込んだのだろうか。しかし天文22年のこととしても、この記事は「信長公記」の桶狭間合戦天文21年の翌年になってしまっている。「信長公記」ではこの合戦は桶狭間の合戦よりもだいぶ前のことのように描かれているにもかかわらずである。桶狭間合戦よりも、13項目も前の部分に置かれているのである。
*「林美作の乱」・・・・・・これは通説通りの弘治2年となっている。干支も合っている。ただ問題なのは、この記事が桶狭間合戦の前に置かれていることである。桶狭間の前にあることは現実の歴史としては正しいのであるが、牛一は桶狭間の年号をこの乱の4年前の天文21年のこととしているのだから、これが前にあるのはおかしい。
*「織田勘十郎信行の御生害」・・・・・年号も、戊午という干支も合ってはいる。先の林美作の乱で、美作にかつがれた信長の弟勘十郎信行は、美作の死後降伏し、しばらくはおとなしくしていたが、後に再び謀反を企てて、信長に自害させられた。したがって、林美作の乱の2年後という、この事件の年号はほぼ正しいものと考えてよいのだが、この事件が、桶狭間合戦の後に置かれている。実際は、林美作の乱も、勘十郎自害も、桶狭合戦の何年か前の出来事であるのに対し、「信長公記」では間に桶狭間合戦が挟まってしまっている。
想像をたくましくして言うなら、この原因としてたとえば次のようなことが考えられる。「林美作の乱」で双方の軍勢は、信長が700足らず、林美作が700ばかり、林に荷担した柴田権六が1000ばかりとある。先の赤塚合戦で信長が動員した兵力が800,今回の700とほぼ変わらない。つまりこれ以前の信長の動員兵力は700~800程度であった。この戦いに信長は勝利を収め、林美作を討ち取り、柴田権六らを改めて配下にするのだが、このことによって、信長は2000~3000の兵を動員できる状況になるのである。つまり、桶狭間での信長軍2000(砦守備兵をも入れれば3000ほど)を成立させるためには、この合戦の記事は桶狭間よりも前に置かなくてはならない。しかし、桶狭間は天文21年に起きたことにしているのだから、弘治4年の織田勘十郎の生害はこれより後でなくてはならない。そのため、桶狭間の記事の直後に勘十郎の生害を持ってきた。想像が過ぎるかもしれないが。
最後の「十四条合戦のこと」は美濃攻めの記事であるが、桶狭間以降のことであり、これは年代的には問題がないといえる。年代に混乱が見られるのは、桶狭間周辺のことなのである。
先に「信長公記」巻首には、掲げられた年号が少ないと述べたが、実は「信長公記」全体で言うと、この作品は几帳面なほど年号を重視した作品なのである。続く巻1~15までは、1巻を一年として、ちゃんと年号を掲げ、月日も記し、きちんと編年的にまとめられている。つまり、全体としてみれば「信長公記」は編年的に整った書物なのである。その全体の構成から見て、巻首のみが意図的なほど、年号を掲げておらず、その上桶狭間の記事を中心として混乱が見られる。そこには、桶狭間をあくまでも天文21年のことにしたかった太田牛一の作為が働き、この時点にこの合戦を押し込んだことにより、年号の錯乱とも言える状況が生じてきたのではないだろうか。
小瀬甫庵は「太閤記」序文で太田牛一を評して「素性愚にして直なる故、始聞入たるを実と思ひ、又其場に有合せたる人、後に其は虚説なりといへども、信用せずなんなりける」と述べている。牛一が他者の意見を受け付けないほどこだわったこと、少なくともその1つは、この桶狭間に関する記述だったのではないだろうか。
さて、枚数が限られているので、ここまで述べてきたことをまとめてしまう。
①牛一が、「桶狭間合戦」を天文21年の事としたのは単なる記憶違いではなく意図的なものであった。
②この合戦が天文21年に行われたことにすると、桶狭間での信長軍の2000余りという数字は、まさにその当時のもので矛盾がなくなる。(というより、桶狭間での信長軍2000を正当化するために、この時点にこの合戦を押し込んだともいえる。)
③「信長公記」の巻首の年号には混乱が見られるが、それらは、現実には永禄3年であった桶狭間合戦を、天文21年に押し込んでしまったために、生じたものである可能性が高い。
④永禄3年での信長の動員兵力は2000余りなどという少ないものではなく、実際の桶狭間合戦の様相については再検討の必要がある。
といったことになる。それでは、なぜ、太田牛一は桶狭間合戦での信長軍を実際以上に少なく2000という数字にしようとしたのであろうか。それは「信長公記」の成立と深く関わってくる問題なのではないかと思われる。だが、そのことについてはまだまとまっておらず、紙数も尽きた。それはまた、次の機会としよう。