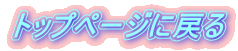*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板の図を参考にした。
*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板の図を参考にした。07年12月15日の「山城の日」で、真篠城、尾崎砦、北松野城に続いて訪れたのがこの蒲原城であった。このルート、ちょうど永禄11年の武田軍の今川領侵攻と同じルートなのではなかったかと思う。このルートを経て初めて駿河湾を目にしたとき、いったい信玄はどのような感慨にふけったものであろうか。蒲原城からは駿河湾の白波を遠望することができ、青空に映えるその風景は心に染み入るほど美しいものであった。
蒲原城は蒲原町役場の北方にそびえている比高100mほどの山頂を中心に展開した山城である。南麓の若宮神社の辺りから山上へ登る道があるので、これをずっと進んでいくと、やがて左手に駐車場が見えてくる。ちなみにこの山の東側にある御殿場広場の辺りも出城の跡であるそうだ。
さて、この駐車場に車を停めて歩き出すと、すぐ脇に4の郭が見えてくる。この道は尾根上を進むようになっているのだが、そのすぐ先には案内板もある。こちら側からのルートはかつての搦め手であったという。
案内板の先には「大堀切」という案内板がある。しかし、案内板の先のヤブに進んでみても、肝心の堀切らしいものはよく分からない。その先にあるのは城とこの尾根との間の自然の沢であり、堀切であるとは思われない。この沢に多少の手を入れて堀切らしくしているのかもしれないが、何しろこの辺はヤブがひどくて詳しいことはよく分からないのである。
3の脇の切り通しを過ぎて、まっすぐ1郭まで行ってみた。1郭は最高所だけあってさすがに見晴らしがいい。駿河湾を一望できるのはもちろん、伊豆半島やその手前の白波、富士山なども見ることができる。絶景というべきであろう。ここを取り合った北条氏も武田氏も、ここでこの光景を見たときには、それぞれ感じるものがあったことであろう。
1郭は20m×60mほどあり、そこそこ広い。現在、ここには神社が祭られている。周囲は切岸加工されているのだが、いきなり城の縁から切岸になるのではなく、左右の縁にはやや低く帯曲輪状になった部分がある。柵列の先に一段低い帯曲輪を配置し、そこを敵を迎撃するための空間として意図していたものであろうか。
1郭の南西側には尾根が続いており、その先に2の郭がある。この辺りヤブがひどく、形状もよく分からないのであるが、登城道の下には帯曲輪が続いていくといった構造になっている。もっともこのあたりには後世の改変があるのかもしれない。
2の先にも数段のまとまった広さの郭があるらしい。南麓からこれらの郭を通って登ってくるのが大手道であったという。しかし、このルート、現在ではかなり荒れており、時間がなかったこともあって、どのような構造になっているのか先の方まで確かめることはできなかった。また、下の方は東名高速道路によって削り取られてしまっている模様である。つまり本来の大手道と呼ばれるルートをたどることは現状ではかなり困難になってしまっているらしい。
1郭の北側の入り口はやや枡形状になっている。その南側の縁には、岩盤をくりぬいて竪堀状に削っている部分がある。よく見ると、人一人が通れるほどのスペースになっている。これも一種の虎口であったものだろうか。降りてみると、その先には小規模な堀切があった。さらにその先に切岸があって、尾根道が延々続いている。これも登城道の1つであったものであろう。
1郭の北側には深さ8mほどもある大堀切がある。そしてその先が善福寺曲輪である。善福寺曲輪との間にあるこの堀切は、底の方は岩盤であったらしく、それを力任せに掘り切っているという非常にダイナミックなものである。草木の繁茂のためにだいぶ分かりにくくなって入るが、壁面には一部石積みらしきものをみることもできる
善福寺曲輪にはさまざまなギミックが復元されていてなかなか興味深い。3箇所の櫓や土塁上の頼りない柵列、さらには塁上の逆茂木群など、かなり珍しいものを見ることができる。中世山城の再現を意図したものだと思うが、しかし、櫓も柵も逆茂木も、どうも模擬くさい感じがする。城塁に逆茂木を配置するといったことは確かにあったものだと思うが、こんな風に並べているのがリアルだとはどうしても思えないのである。そんなわけで、私はこの城の再現物はどうも好きになれない。こんなものがなくても、城の本来の遺構だけで十分なほどに遺構の充実した城出あると思うのである。
善福寺曲輪の北側城塁はやはり鋭い切岸となっている。その下の方にはかなり充実した石垣が見られ、防御に意を払っている様子を伺うことができる。ここにはA,Bの腰曲輪があるが、これらの腰曲輪の縁部には土塁が積まれているので、一種の横堀と見てよいかもしれない。特にAの部分は入り口が土塁によって狭められており、一種の枡形構造であったかとも思われる。Bの郭の東側は自然地形となっているが、その下はやはり横堀となっている。
今回の訪城で見たのはざっとこれくらいである。実際にはまだまだ郭も遺構もあるようだが、とりあえず歩いた範囲だけを図にしてみた。ヤブがひどいといったこともあり枝葉の方は把握できない。しかし、この中心部だけでもそれなりにまとまった遺構を見ることができる。軍事的拠点城郭というのにふさわしい城であるといっていいと思う。
蒲原城は今川氏や北条氏・武田氏によって番城として用いられ、北条氏・武田氏によっても大規模に改修されている城だという。しかし、これぞ北条氏!あるいは武田氏!といった印象は受けない。山の地形なりにそこそこの規模の城を築いたらこんな感じになったといったところであろうか。もしくは、天然の要害であったために、特別な構造を新たに築き上げる必然性はなかったということであるのかもしれない。