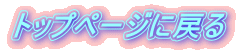矢板市
*参考資料「日本城郭体系」「那須の戦国時代」「栃木県の中世城館跡」
泉城(高城・矢板市東泉)
 泉城は、内川の東側の比高40mほどの山上にあった。瑞雲院のすぐ東側の山である。雨が降ってきたため、今回は遠望だけ。
泉城は、内川の東側の比高40mほどの山上にあった。瑞雲院のすぐ東側の山である。雨が降ってきたため、今回は遠望だけ。
泉城は天正19年(1591)、岡本讃岐守正親によって築かれたものであるというから、わりと新しい城である。岡本氏はもともとは塩谷氏の被官であったが、小田原の役の際、いち早く秀吉の元に参陣したので、その恩賞として、泉15郷を拝領してこの城を築いたという。
しかし、岡本氏は正保元年(1644)、一族内紛のため、改易となった。
「栃木県の中世城館跡」によれば、山上に本丸、段階的に二の丸、三の丸があるという。また「戦国末期の築城のため土塁、濠などが少ない」とあるが、そんなものなのだろうか。戦国末期の築城だからこそ派手な土塁や空堀があってもよさそうな気がするのだが・・・・・・。
岡城(矢板市片岡字城山)
 片岡の明本寺の東200mほどの所である。内川が江川と合流する地点の比高7,8mほどの河岸段丘上に築かれている。3郭構造で、東の先端から連郭式に配列されているが、畑地化などにより、遺構はかなり破壊されている。
片岡の明本寺の東200mほどの所である。内川が江川と合流する地点の比高7,8mほどの河岸段丘上に築かれている。3郭構造で、東の先端から連郭式に配列されているが、畑地化などにより、遺構はかなり破壊されている。
城主は塩谷安芸守と言われているので、川崎城の支城の1つであったものだろう。天正年間になると、岡民部兼定が居城としていたという。
岡氏も塩谷氏の家臣で、天正13年(1585)の薄葉ヶ原の合戦では、宇都宮方として合戦に参加し、那須氏と戦っている。
塩谷氏が滅亡した後は、宇都宮氏に仕えたという。
豊田館(稗田城・矢板市豊田字寄居)
那須与一の兄である九郎朝隆が稗田(現在の豊田)に分地されて、稗田氏を名乗った。その居館が稗田城(豊田館)である。かつては堀などが残っていたと言うが、現在は水田となってしまっているために、遺構は湮滅に近いという。正確な場所もよく分からない。
稗田氏は沢村氏と共に那須氏家臣として活躍した。
松ヶ嶺城(根小屋城・上太田城・矢板市下太田)
 松ヶ嶺城は東北自動車道の矢板北PAのすぐ北側の比高50mほどの山上にあった。城のすぐ東側下を中川が流れている。
松ヶ嶺城は東北自動車道の矢板北PAのすぐ北側の比高50mほどの山上にあった。城のすぐ東側下を中川が流れている。
城を最初に築いたのは塩谷伯耆守孝綱であり、永正年間のことであった。しかし後には岡本氏の居城となった。岡本氏といえば、泉城の城主であるが、泉城に移るまでの岡本氏の居城がこの松ヶ嶺城であるという。
「栃木県の中世城館跡」によれば、頂上に本丸を置き、段階状にいくつかの郭を配置しているという。東側には井戸跡、西南部の大手には石塁もあるということである。
山田城(根小屋城・矢板市山田)
 山田城は泉城の900m東側にある。やはり比高40mほどの山上にあった城であった。山田公民館の北西500mほどの位置である。
山田城は泉城の900m東側にある。やはり比高40mほどの山上にあった城であった。山田公民館の北西500mほどの位置である。
戦国期の山田城の城主は山田筑後守業辰で、川崎城塩谷氏の家臣であった。東の箒川を渡ると、すぐそこは那須一族の勢力範囲であり、那須勢力との境目の城でもあったと思われる。
天正13年、この城の近くで那須勢と宇都宮勢とが激突した。薄葉ヶ原合戦である。この戦いで山田業辰は討死したという。
「栃木県の中世城館跡」によると、50×90mの本丸、その東側下に88m×110mの二の丸、さらにその東南下に最大幅150mの三の丸があるという。三の丸には井戸跡がある。その南低地の「内根小屋」が居館地区で、東側低地には水堀もあったという。
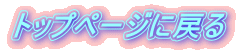
 泉城は、内川の東側の比高40mほどの山上にあった。瑞雲院のすぐ東側の山である。雨が降ってきたため、今回は遠望だけ。
泉城は、内川の東側の比高40mほどの山上にあった。瑞雲院のすぐ東側の山である。雨が降ってきたため、今回は遠望だけ。 片岡の明本寺の東200mほどの所である。内川が江川と合流する地点の比高7,8mほどの河岸段丘上に築かれている。3郭構造で、東の先端から連郭式に配列されているが、畑地化などにより、遺構はかなり破壊されている。
片岡の明本寺の東200mほどの所である。内川が江川と合流する地点の比高7,8mほどの河岸段丘上に築かれている。3郭構造で、東の先端から連郭式に配列されているが、畑地化などにより、遺構はかなり破壊されている。 松ヶ嶺城は東北自動車道の矢板北PAのすぐ北側の比高50mほどの山上にあった。城のすぐ東側下を中川が流れている。
松ヶ嶺城は東北自動車道の矢板北PAのすぐ北側の比高50mほどの山上にあった。城のすぐ東側下を中川が流れている。 山田城は泉城の900m東側にある。やはり比高40mほどの山上にあった城であった。山田公民館の北西500mほどの位置である。
山田城は泉城の900m東側にある。やはり比高40mほどの山上にあった城であった。山田公民館の北西500mほどの位置である。